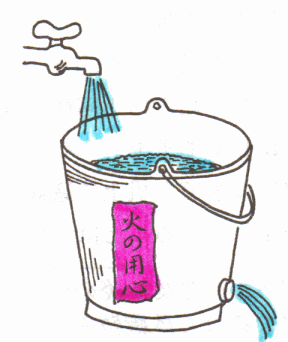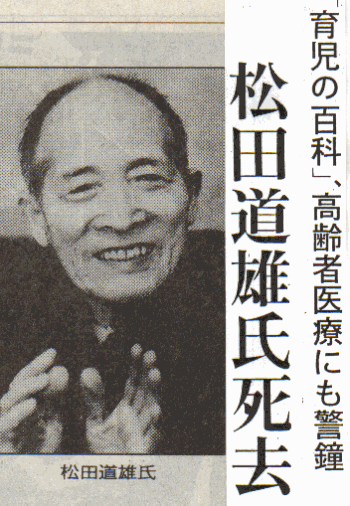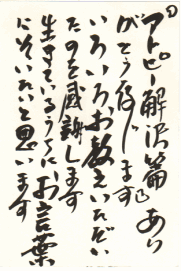|
|
|
第4章 ステロイドの薬害
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
ステロイドホルモンとは、<C17H28>という、ステロイド核をもつホルモンの総称で、アトピー性皮ふ炎の「治療」と称する作業に用いられるのは、そのうちの「副腎皮質ホルモン」の外用薬(塗り薬)です。腎臓の上に小さな臓器がくっつくようにあって、それを副腎と呼びます。副腎は薄皮まんじゅうのように皮質と髄質から成り立っていて、この皮質から分泌されるホルモンを副腎皮質ホルモンといいます。このホルモンは、外界の刺激に対する生体の防御反応を抑制し、「戦いをやめよ」という「停戦命令」として機能し、個体を環境に順応させる働きがあります。
これと類似の構造と類似の機能を持つ化学物質を人工的に化学合成することができ、ステロイドの薬剤にはそれが主成分として含まれています。ステロイドが開発された当初の1950年代には劇薬指定は無かったのですが、医療関係者が魔法の薬として、さまざまな病気に対してあまりにも安易に使ったため、副作用の被害が相次ぎ、厚生省に集まる全国の副作用被害報告の、10%以上をステロイドが占めるという事態になりました。
| 20年前(1976年)に出された健康雑誌に、ステロイド剤によって引き起こされた被害が特集されており、特に感染症を併発して悲惨な状態を招いている実態や、リウマチに使われて身体をボロボロにされた体験が、「奇跡の薬にひそむ魔性」とか「乱用がこわーいステロイド剤」というタイトルで紹介されています。 (アトピー・ステロイド情報センター機関誌No.27 P.18 1997年5月) |
そこでやむなく厚生省は1976年、今から20年前にこれを劇薬に指定しました。しかしその後も、ステロイドの薬害は増えるばかりです。
ステロイドがどのように恐ろしいか、皮ふ科医自身が語っています。1997年4月、岡山で開かれた日本皮膚科学会の市民公開講座で、パネリストの1人であった国立O大学皮ふ科のT氏は、「ステロイド外用剤の適切な使い方」と題する講演を行い、その冒頭で満場の聴衆に次のように警告しました。(記録が残っていないので匿名とします)
| みなさん、ステロイド外用剤を使うときは、きちんと医師によってアトピー性皮ふ炎であるという診断を受けて下さい。これはとても大切なことです。アトピー性皮ふ炎ではない人にステロイドを塗ると、たいへんなことになるんですよ。 (T氏 国立O大学皮ふ科 アトピー市民公開講座 講演 1997年4月) |
聴衆はもちろん、アトピー性皮ふ炎で困っているから来ているわけで、その人たちに向かってT氏は、「私たち皮ふ科医は、アトピー性皮ふ炎ではない人に塗ったらたいへんなことになる薬を、あなた方には塗るのだ」と言ったわけです。もちろん氏は、断固として正しいことを言っているつもりです。その思考のバックボーンは「アトピー体質論」です。アトピー性皮ふ炎の人は遺伝的な素因を持っており、つまり、アトピー性皮ふ炎は不治の病である。その苦しみを和らげるために、アトピーでない人に塗ったらたいへんなことになる薬剤が容認されるのは当然である。それを上手に使うことこそ皮ふ科医の使命である、という考え方です。そのあとT氏は、ステロイドは皮疹の赤いところに塗るんですよ、はみ出して赤くなってないところに塗ってはいけませんよ、ステロイドは軽く塗ればいいんですよ、擦り込んではいけませんよ、等々、ステロイドの塗り方を懇切丁寧に説明しました。
T氏の話には、もうひとつ皮ふ科医に特徴的な思考法が現れています。それは、「アトピー性皮ふ炎です」と診断することで、皮ふ科医たちは何か仕事をしたと錯覚していることです。白衣を着て患者を診察し、皮膚科学会などで決められたマニュアルにしたがって、「アトピー性皮ふ炎」と認定する。これは自分でもたしかに、何か意味のある熟練の業を為したかに思えることでしょう。しかしそれは勘違いというもので、実際は、「アトピー」とは「奇妙な」という意味ですから、眼前の皮ふ炎を「アトピー」と認定することは、「これは正真正銘の奇妙な皮ふ炎です」と認定しているだけのことであり、その行為の真の意味は、「これは私には分からない皮ふ炎だ、ということが分かった」ということでしかありません。
| 1994年に発表された日本皮膚科学会の「アトピー性皮ふ炎の診断基準」は世界で初めての診療を中心にした、非常に重要な診断基準であり、長期間のディスカッションを経て作成されたものだけに、世界的にも通用すると考えられる。 (上原正巳 滋賀医大皮ふ科 第6回日本アレルギー学会シンポジウム記録集 医科学出版社 1994) |
何が奇妙であり何が奇妙でないか、について長期間の討論を経て、世界に冠たる診断マニュアルを作ったというわけですが、それほど自慢することではないのです。
4−2 ステロイド外用薬の作用
皮ふは体の防壁であり、皮ふの炎症は、皮ふ細胞が外敵と戦っている姿です。人間の体には、外敵に対して「戦え」という指令と、「戦いをやめよ」という指令とがバランスよく配されています。そのバランスを保つことが生命活動の巧みさでもあります。
そのうちの、「戦いをやめよ」という指令は、副腎皮質ホルモンが担っており、ステロイド軟膏はそれと類似のものを人工的に合成して外用の軟膏(塗り薬)という形にしたものです。それを炎症が起きている皮ふに塗ると、外界の刺激に対する防御反応が抑制され、炎症は劇的に「消えて」しまいます。
製薬会社はこの作用をもって、「ステロイドには抗炎症作用がある」と表示し、医者たちもそれを慣用句としています。しかしこれは誤解を生む表現と言わねばなりません。むしろ、意図的に作られた欺瞞的表現だと言うべきでしょう。なぜなら、抗炎症作用の「抗」という字は「戦う」という意味ですが、ステロイドは誰とも戦わないからです。
そもそも、「炎症と戦う」ということ自体が、コンセプトとして成立しません。炎症とは、身体が外敵と戦っている戦場の風景であり、戦いそのものの姿であって、戦う相手ではありません。ステロイドはその「戦いそのもの」を無くします。どうやって戦いをなくすのか。それは、外敵と戦っている味方にニセの停戦命令書を渡して無条件降伏させることで、戦いそのものをなくしてしまうのです。味方をだますわけです。
しかし、外敵に攻撃されているときにまず為すべきは、その外敵を排除することのはずです。原因がわからないから、という理由でそれをせずに、味方をだましてでも無条件降伏してしまう、これが「アトピー性皮ふ炎にステロイドを塗る」ということです。これを「医薬学」の業界用語で「炎症と戦う」と言っているのです。
1度や2度はそれで済むかも知れませんが、連用すればステロイドは免疫機構のバランスを破壊します。これは、そうなるかも知れない、ということではありません。必ずそうなるのです。それがステロイドの「作用」だからです。作用と言い、副作用と呼ぶのは人間の勝手な都合であって、薬にあるのは作用だけです。ステロイドは免疫系の正しい働きを「破壊すること」を「目的」としています。ですから、ステロイドに発売当初から薬害が絶えないのは当然なのです。
4−3 ステロイドの常用とIgEの増加
ステロイドによる免疫系の破壊は、具体的にはIgEの天文学的増加という形で起こってくるようです。
| 血清IgE濃度 アトピー性皮ふ炎患者の70〜80%に血清IgE濃度の上昇がみられ、臨床症状の重症度と平行する。しかし、治療によって臨床症状が改善されても、短期間では低下傾向を示さないので、治療効果の指標とはなりにくい。 (日本アレルギー学会 皮ふ科構成員共同執筆「アレルギー疾患治療ガイドライン」 ライフサイエンスメディカ社 1994) |
| 執筆者:青木敏之:羽曳野病院/阿南貞雄:吉田彦太郎:長崎大/池澤善郎:横浜市大/今村貞夫:京大/上原正巳:滋賀医大/岡部俊一:平鹿総合病院/小川秀興:順天堂大/久米井晃子:桜井美佐:中山秀夫:済生会中央病院/新谷真理子:本田光芳:日本医大/徳田安章:東京医大/新村真人:慈恵医大/濱田稔夫:大阪市大/早川律子:名大/松田三千雄:釧路赤十字病院/山本一哉:国立小児病院/山本昇壮:広島大/吉池高志:順天堂大浦安病院 |
これは皮ふ科の指導的な医者たちが、一般の医者向けの教科書として書いたものですが、この文章は本質的なことを明らかにしています。それは、皮ふ科医はIgE値を臨床症状とは考えていないということです。皮ふ科医にとってIgE値とは、臨床症状と平行したり離れたりする何ものかではあるが、臨床症状ではないのです。だいたいそんなものは、もともと本人の素因だろうよ、というのが皮膚科学会の定義でした。
そしてこのような理解は、実際の治療における重要な分岐点となります。すなわち、皮ふ科主流派による治療法とは、あれこれ並べてみても、結局の所は「ステロイドを塗る」ということですが、それによって臨床症状が改善されている、という主観的判断の一方で、IgE値という客観的な指標が上昇したとしても、皮ふ科主流派にとってはそれでよいのです。実際、皮ふ科における日常的な治療はそのようなものであり、IgE値が上がろうが下がろうが気にすることはない、とこの教科書は一般の医者に告げています。
皮ふ科主流派から、一般国民には次のようなメッセージが発せられています。
| 本書のタイトルを、「アトピーは治る」としましたが、より正確に言えば「アトピー性皮ふ炎の皮ふ症状は治すことができる」ということです。残念ながら現在の医療技術では、アトピー体質そのものを治すことはできません。 (西岡清 東京医科歯科大 皮ふ科 「アトピーは治る」講談社ブルーバックス 1997 まえがき より) |
「皮ふ症状は治すことができる」ことをもって、「アトピーは治る」と表現する、表現してよい。これが皮ふ科主流派の見解であり、業界の慣行です。みなさんは、ぜひ誤解のないようにしましょう。しかし一方、こういう告白もあります。
| 最近皮ふ科医らによって「アトピー性皮ふ炎の治療研究会」が組織された。その第1回シンポジウムで、私はカラー写真による皮疹の評価をした。これをまとめている際に、そもそも皮疹というものは、単独でアトピー性皮ふ炎の治療効果の判定の目安となりうるか、という基本的な疑問を抱いた。 (深谷元継 国立名古屋病院皮ふ科 「アトピーマガジン」トータルケア社1996) |
20年前に厚生省がステロイドを劇薬指定した後も、ステロイドの被害はやむことなく、ステロイドによって
「皮疹を治してもらった」
多くの人々が、重い後遺症に苦しみ、被害者の会を結成し、裁判まで起こして戦ってきています。ですから、今頃まだこんなことを言っているのか、ということですが、皮ふ科の主流派が皮疹しか見ていない現状では、深谷氏のような医者が育ってくるのも当然かも知れません。しかし氏はその後、極力ステロイドを使わない治療を試みているようです。
いずれにせよ、皮ふ科主流派による治療、すなわちステロイド治療では、IgE値が短期間に下がることはないということです。
しかし実際は、IgE値は下がるのです。
| 昭和30年(1955)以来、私は皮ふ病治療にステロイド軟膏を使ったことはない。温泉・水治療では、皮ふの反応としての炎症を忌避することなく、むしろ炎症を合目的的に推進して完結させようとする。弱いの、強いのといってステロイド軟膏をだらだらと長期間使用した患者では、それを使用し続けた期間ぐらいの療養期間を要する。これは、覚醒剤や麻薬の中毒や、アルコール依存症の患者と同様である。 (野口順一 盛岡市上田病院 「アトピー性皮ふ炎の温泉・水治療」 光雲社 1995) |
野口氏は、炎症は皮ふが外敵と戦っている勇ましい姿で、それをステロイドで抑えることは、治療ではなく粉飾だと考える、70才を越える老練の皮ふ科医です。そして氏は学会において、「たびたびステロイドの害を訴えてきたが、学会主流派に無視されてきた。学会が製薬会社の寄付で運営されている現状では仕方ないのか」と慨嘆します。
しかし野口氏はこの書物の中で、ステロイドをやめさせ温泉療法などをすすめていくと、なるほど一時的には皮疹は悪化するが、それに耐えているとやがて皮疹は軽快し、それとともにIgE値が低下するという、重要な事実を多数報告しています。(単位IU/ml)
| 表 皮疹の改善につれてIgE値は下がる (盛岡市上田病院皮ふ科 野口順一氏 前掲書より) |
||||
| 初診時 IgE A |
皮疹 軽快時 IgE B |
減少比 B/A % |
所要期間 | |
| 3才 男 | 7500 | 2800 | 37 % | 19ヶ月 |
| 3才 男 | 19534 | 7398 | 38 % | 7ヶ月 |
| 12才 女 | 1600 | 590 | 37 % | 9ヶ月 |
| 13才 女 | 1411 | 735 | 52 % | 3ヶ月 |
| 21才 男 | 63236 | 20263 | 32 % | 7ヶ月 |
| 30才 男 | 19192 | 7132 | 37 % | 7ヶ月 |
| 36才 男 | 8651 | 7178 | 82 % | 7ヶ月 |
| 平均17才 | 18374 | 6584 | 35 % | 8.4ヶ月 |
話をシンプルにするために単純平均をとれば(表のいちばん下段)、このデータは、治療の方法によっては、IgE値は8ヶ月ほどで3分の1になることを明らかにしています。アトピー性皮ふ炎の治療で8ヶ月は「短期間」と言えます。
ですからこのデータは、「IgE値は短期間では下がらないから、治療効果の指標とはなりにくい」という皮ふ科主流派の経験則に対する明快な反証となっており、実際、野口氏は治療の指標として使っているわけです。
そして、わざわざ岩手県まで野口氏の治療を受けに来る人は、それまでは「皮ふ科主流派の治療」を受けていたでしょうから、時系列から見ても、治療法を変えればIgE値は下がるということです。
皮ふ科主流派は、IgEは業務外だと決め込んでいますから、このデータを見ても何も感じないでしょう。第一彼らは、野口氏の話を聞こうともしません。しかしこのデータは、「現代日本のアトピー性皮ふ炎」のジグソーパズルを完成させる重要な切片のひとつであり、これをそこらに放り出したままにしている人々が、アトピーのパズルを完成させることは、今後とも期待できません。
皮ふ科主流派と野口氏とが提示した事実は、以下のとおりです。
| 皮ふ科主流派 | ステロイドを塗っていると IgE値は下がらない |
| 野口氏 | ステロイドをやめると IgE値は下がる |
この2つの事実を素直で洞察力のある目、すなわち、「なんだ王様はハダカじゃないか」と笑った子の目で見れば、状況は明快でしょう。犯人は探偵だった!という推理小説のように、ステロイドがIgEを増大させていると考えれば、すべて腑に落ちるのです。
IgEを増加させる要因は、寄生虫などいろいろあります。結核になっても増えます。虫に刺されても増えるのかも知れません。ステロイドは、それらIgEを増加させる要因のひとつだと考えられます。状況はそう語っています。
皮ふ科主流派は、「そんなことを言うなら証拠を出せ」と言うでしょう。立証責任は文句を言うやつにある、というのが薬害に対する「医薬学官」業界の常套的な対応だからです。危険だと証明されるまでは危険ではない、これが、薬害エイズで、帝京大の安部氏やミドリ十字が非加熱血液製剤の在庫一掃セールをした論理でした。しかし、そのような論理では国民(顧客)の安全は保障されません。話は逆で、安全だと証明されるまでは安全でないのです。ステロイドという薬剤を30年にわたって国民の皮ふに擦り込む前に、ステロイドがIgEの産生機能を暴走させることはない、などなどの安全性の証拠をこそ、「医薬学」業界は国民(顧客)に提出すべきだったのです。薬とは、そういう安全性を確認してから使われるべきものです。しかし業界はそのことを、30年間にわたって無視してきました。私たちは今、その結果を見ているのです。
4−4 IgEが増大するプロセス
さて、ステロイドを塗るとなぜIgEは増えるのでしょうか。筆者にはそのメカニズムを調べることはできませんが、そのプロセスを推理することはできます。
そもそも、ステロイドは免疫系の情報破壊を「目的」として作られた薬です。ですから、ステロイドによって免疫系に異常が生じるのは当然のことです。その異常はまず、「皮疹が劇的に改善される」という形で起こります。これはまさに異常事態です。ステロイドはニセの停戦命令として作用し、それが擦り込まれたところの戦い(皮疹)を消滅させます。
その作用が、その場所に限定されていれば全身的な影響は生じないでしょう。しかし、皮ふに擦り込まれたステロイドは、やがて血液にとけ込んで血流にのって全身をめぐります。つまり、出所不明の「ニセの停戦命令」が擦り込まれ、それが血中にあふれるという事態が、日常的に繰り返されるようになります。
すると生体の免疫系には、やがて、バランスを回復しようとするフィードバック(元に戻そうとする力)が働きます。おそらく、何かの事情で停戦命令が度を超えて過剰になったときには、戦闘部隊を増強してバランスをとる安全装置が、生体のどこかにあるのです。それが生体の正しい反応というものです。アトピー性皮ふ炎が発生していたのは、何らかの外敵がいたからで、それはまだ排除されていませんし、ほかの外敵が攻めてくるかも知れません。生体は、バランスを回復するために戦闘部隊を増強し始めます。
あるいは、皮ふでひと仕事したステロイドは、すでに効き目を失った「ステロイドの残骸」となって血中に入るのかも知れません。それはたとえば、「とうがらし」を長い間ほおっておくと、形はあるが辛くないという「気の抜けた」状態になるようなものです。しかし、もしそうだとしても、脳(脳下垂体)にはステロイドの「化学的な形」は認識できるが、「気が抜けているかどうか」までは認識できないとすれば、やはり脳にとって状況は、「停戦命令」が異常に血中にあふれていることになります。ですから脳は「戦闘部隊の増強」を指令するでしょう。
どちらであるにせよ、生体の正常なフィードバック機能によって、戦闘部隊は増強されます。戦闘部隊が増強されるとどうなるか。再び炎症が起きてきます。なぜなら敵はまだ排除されていないからです。すると、外部からのニセの停戦命令が、もっと強い命令に書き換えられます。具体的には、「この薬は効き目が落ちてきたので、新しい薬を出しましょう」と診察室で言われて、さらに強いステロイドが、さらに大量に処方されることになります。
あとは繰り返しです。ブランコをこいでいるようなもので、ステロイド、ステロイドと片側に少しずつ勢いをつけていると、ブランコは両側にどんどん大きく振れてきます。戦うべきか戦わざるべきか、というバランス点は、らせん階段を上るようにどんどん上昇していきます。そして、現実問題としてIgEが急増していることから判断すれば、ステロイドの反対側にある戦闘部隊の、少なくともひとつは、IgE部隊でしょう。
「IgEを産生しやすい人がいるんだ、それは生まれつきの素因なんだ、みんなで相談して、そう決めたじゃないか」と皮ふ科主流派は主張するでしょうが、上述のプロセスは誰にでも起こります。疑う人は自分で確かめることができます。あなたの皮ふに毎日ステロイドを塗っていれば、やがてあなたのIgEは暴走し始めるでしょう。なにしろ、アトピーでない人に塗ったらたいへんなことになる、と皮ふ科主流派の折り紙付きの薬なのですから。
しかし、実はこの実験はすでにたくさん行われています。アトピー性皮ふ炎の子供に、素手で一生懸命ステロイドを塗っているうちに体調をこわした母親がたくさんいます。また、ステロイドが開発されてもてはやされた頃、化粧品にステロイドが入れられたことがあり、ミクロ○○パスタという眉毛を濃くする養毛剤に入れられたこともあります。それらの化粧品は、多くの女性の健康な肌に重大な損傷を与える結果となり、50代、60代の女性でいまだに後遺症に悩まされている人も大勢います。そのころはまだIgEの測定技術は確立されていませんでしたが、もし測定されていたら、その人たちのIgE値が高くなっていることが見つかったはずです。
4−5 ステロイドのリバウンド
ステロイドを常用している人々の体内では、出所不明のニセの停戦命令と、自前の戦闘部隊とが、通常の何十倍、何百倍も高いところで危ういバランスをとろうとしています。IgEの正常値が
100ユニット程度であるのに対し、アトピー性皮ふ炎の人のそれは、10,000ユニットとか
20,000ユニットとかになるほどです。また一方で、外部からいくらでも停戦命令がやってくれば、自前の停戦命令(副腎皮質ホルモン)の出る幕はありませんから、副腎皮質の機能はしだいに衰えてゆきます。
このような不具合に気づいた少なからぬ人々が、ステロイドをやめようとチャレンジします。それは「らせん階段」のてっぺんから飛び降りるようなもので、ステロイドをやめてしばらくすると、ニセものとはいえ一応は停戦命令であったものが急に減って、体内には戦闘部隊ばかりが残りますから、皮ふ細胞はあらゆる刺激に対して戦い始めます。はげしい炎症が起こり、皮ふが破れ、そこから体液が流れ出し、発熱、寒気、強い痒みが全身をおそいます。入浴すると、皮ふのあらゆる傷口やヒビ割れから、体液とともにステロイドの残滓や基材が湯の中にしみ出して、強い薬臭が浴室に充満します。戦闘部隊は全身を巡ってあらゆる刺激と戦いを始めますから、ちょっと衣服でこすれたぐらいでもはげしい炎症となり、今まで炎症がまったくなかったところにも炎症が起こるようになります。これがリバウンド(はね返り)です。
ステロイドを使うことによって起こる現象は、業界筋が「副作用」と呼ぶものも含めて、すべてステロイドの「作用」です。そして、ステロイドを使わなくなったことによって起こるリバウンド現象は、ステロイドの「反作用」です。作用があれば反作用があるのは物理学では当然のことで、リバウンドは、ステロイドから脱出するために避けて通れぬ、治癒への必要なプロセスです。ですから、このようなリバウンドの状況は、ステロイドを使わない、盛岡市上田病院の野口順一氏などにとっては、別に驚くことではありません。しかし、皮疹を改善することをもって天職と心得る皮ふ科主流派には、このリバウンド状態は言語道断の「見るも哀れな状態」としか見えません。
| 、、、
と同時に「ステロイド外用薬には怖い副作用がある」という俗説もまた広まってきているようです。ステロイド外用薬の使用を拒否した結果、見るも哀れな状態にまで悪化している患者さんに出会うこともしばしばです。確かにステロイド外用薬には副作用があります。しかしその副作用のほとんどは使用法の誤りによるものであり、医師の指導のもとに上手に使用すれば、まったく副作用を起こさずにアトピー性皮ふ炎を治療することも可能です。それどころかステロイド外用薬は、アトピー性皮ふ炎の治療には必要不可欠な薬剤と言っても過言ではありません。 (川島 真 東京女子医大皮ふ科 「アトピー」有斐閣 1990) |
使い方が悪いせいだ、とは、医者にはまるで責任がないかのようですが、川島氏はここで、微妙な言い回しで医者の責任にも言及しています。すなわち氏は、「患者の使い方」が悪いとは言っていません。これは、使い方が悪い医者もいるという意味です。実際、「町医者のレベル」では、氏も呆れるような話がたくさんあるのだと思われます。
この文章には、もうひとつ注意すべき言い回しがあります。それは、「副作用なしに治療することが可能です」と100%断定せずに、「治療することも可能です」と部分的な表現をしていることです。これは、「治療できることもあるが、できないこともある」という意味で、たとえ使い方の上手な医者、すなわち、氏を始めとする皮ふ科主流派の指導に従っても、うまく行かないこともあるという、正直な告白となっています。
結局、ステロイドについての川島氏の主張は、「この薬には副作用があります。でも、うまくいくこともあります」というものです。しかも、「うまくいく」とは皮疹がよくなることでしかない、というのが皮ふ科主流派の見解でした。
ところが川島氏はここから、「それどころか」という接続詞を用いて場面の転換をはかり、「ステロイドは治療には必要不可欠なのだ」と飛躍します。いきなりそんなことを言い出されても、「うまくいくこともあります」程度の薬が、なぜ「患者にとって」必要不可欠なのかは、この文章からはさっぱり分かりません。「昭和30年以来、ステロイドを一度も使ったことはない」(前掲 野口氏)という皮ふ科医だっているのです。必要不可欠なのは患者にとってではなく、「医者にとって」ではないかと思われます。
ステロイドを使わない治療を実施している古座川国保明神診療所の森田貴久子医師は、医学教育を批判して次のように述べています。
| 次に医学教育ですが、「アトピーにはステロイド」とこれは常識です。皮ふ科の教科書では、「アトピーにはステロイド」です。ステロイドを使ったらあかん、といってしまったら、治療する方法がないですよ。アトピー以外のほとんどの皮ふ病もステロイドです。誰が医者になってもステロイドを使うということです。 (森田貴久子 古座川国保明神診療所 「アトピー・ステロイドを考える講演記録集」 アトピー・ステロイド情報センター編 1995) |
いずれにせよ、皮ふ科医から「見るも哀れ」と同情されながらも、「ほっといてくれ」と頑張って、とにかくこのようなリバウンドに耐えて、ステロイドからの脱出に成功した人がたくさんいます。このあたりの状況は、「身を捨ててこそ、浮かぶ瀬もあれ」ということわざがピッタリで、川の淵でおぼれて、ステロイドというワラにもすがっている時、思い切ってそのワラを捨てれば、身はいったんは深淵に呑み込まれますが、やがて流れに運ばれて、浅瀬にポッカリと浮かぶのです。
しかし、ステロイドをやめただけでは、ステロイドが完全に抜けてくれるとは限りません。多くの人々は、ステロイドを塗らなくても何とか暮らせる、という状態になっただけで、体内にステロイドを抱え込んだままの、「ステロイド後遺症」の不安定状態にとどまっています。そして、そこから先は「こうなったのも、そもそも私がアトピー体質だからだ」とあきらめてしまっています。
4−6 ステロイドの後遺症
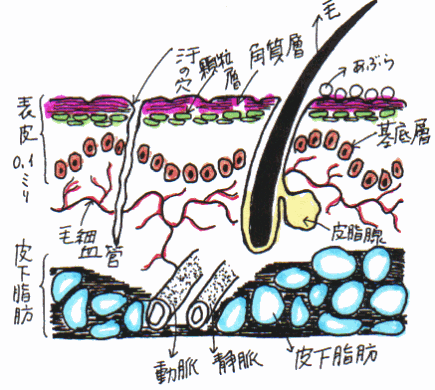 |
ステロイドは皮ふにすり込まれると、皮ふ細胞の炎症を消し、そこから血流に入って体内をめぐります。それは前述したように、免疫機能を暴走させてIgEを増大させるでしょう。しかしそれでも、そのステロイドの大半は、やがて肝臓や腎臓で処理されて、体外に出てくれます。しかしステロイドは脂溶性の物質ですから、一部は、皮ふから血流へ浸透してゆく途中で、皮下の脂肪層につかまって皮下脂肪の構成要素となってそこにとどまります。皮下脂肪にとらえれるのはごく一部だとはいえ、次から次へとステロイドは擦り込まれてくるわけですから、皮下脂肪に蓄積されるステロイドの量は、しだいに増えてゆきます。
しかもこの脂肪層というものはゴム風船のようなもので、ひとつひとつの脂肪細胞の中に脂肪分をいくらでも取り込むことができ、限界がありません。だから相撲の小錦のように体重300キロに近い人もできてくるわけです。脂肪分の代わりにステロイドのような脂溶性の物質が入ってきても、同じことが起こります。ステロイドも、塗れば塗るほど皮下脂肪に溜まるのです。
ところが、なんとも妙なことを言う人もいます。
| 出尽くしたら治る?
原因不明の病気に対して、出尽くすもなにもないわけで、出てるのは自分の体液なんだけど、どうもステロイドが体内にたまっていて、それが出てると患者さんは思うみたい。だけどステロイドは体内にたまりません。 ステロイドが本当に体内に蓄積すると言うのなら、1回塗ったらあとは一生塗らんでも効果を発揮するはずでしょ。たまらないから毎日塗ったりしなくちゃならないわけで、そんなことあり得ない。みんな錯覚。 (江部康二 京都高雄病院 「アトピー治療の新しい道」 風濤社 1996) |
物理現象には時間がかかります。いったん体内にとりこまれたものは、排出されるまでに時間がかかります。「たまらない」ということは、ほとんど時間ゼロで排出されるということですが、そういう物理現象はありません。ステロイドの体内滞留時間はどのくらいか、1日か、3日か、1ヶ月か、1年か、10年か、それが問題なのです。
また、脂肪層の構造の一部に組み込まれたステロイドが、そこから抜けてもう一度皮ふ層にまで上昇し、そこの炎症を消すことはほとんど起こりません。あるいは先述したように、すでにステロイドの効き目が失われている可能性もあります。ですから、「たまるんやったら、1回塗れば一生もんやないか」などという稚拙な理屈も成り立ちません。
しかしそもそも、「ステロイドは体内にたまるや否や」などということを、医者たる者がいつまでも机上で議論していること自体がおかしいのです。皮下脂肪にステロイドが滞留していることは、皮脂を採取して物理的に検出できることだからです。
| アトピー性皮ふ炎の児童の体脂肪率を生体インピーダンス法で調べた。その結果、重症になるほど体脂肪率が高いことがわかった。このことの主原因がステロイド外用剤の影響である可能性は否定できない。 (小田島安平 都立広尾病院小児科ほか 小児アレルギー誌V.10-4 P.491 1996) |
これは皮脂を採取したわけではなく、外部から皮下脂肪の量を電気的に測定しています。ステロイドが脂溶性の物質だということは、ステロイドは脂質と似た物質だということですから、ステロイドも皮下脂肪も、インピーダンス測定器には類似のものとして検知されるでしょう。つまり、皮下脂肪にステロイドが蓄積していれば、上記のような測定結果が得られるはずです。小田島氏の懸念は正しいと思われます。
ステロイドを連用している人の皮ふは、ステロイドが蓄積されて肥厚し、黒ずんで固くなってゆきます。脂溶性の物質が、体内の脂肪層に入ってしまうときわめて抜けにくく、いつまでも後遺症が続くことは、25年前のカネミ油症事件(PCB)や、最近のダイオキシンの体内蓄積などでも明らかです。
ダイオキシンについてはピコグラム(1兆分の1グラム)の量まで測定できています。ですから、その百万倍のマイクログラム以上はある、皮下脂肪中のステロイドを測定することなど、ごく容易なことです。しかし現実には、そのような測定は皮ふ科臨床関係者の間では為されていません。そもそも、ステロイド外用薬が皮ふに残存する、という発想がないのでしょう。
ステロイドをやめてから何年もたつ人でも、肥厚した脂肪層にステロイドが滞留しており、それは少しずつ血流に溶けだしています。脂肪層に滞留しているステロイドは、もはや局所的に皮疹を治すことはできませんが、全身的には、ステロイドを塗っていたときと同じような作用を発揮し続けて、身体の免疫機能を混乱させ、副腎の機能の回復を遅らせます。これが、ステロイドの後遺症です。
現代日本のアトピー問題の半分は、ステロイド後遺症の問題ですから、次節で述べるような、ステロイド残存量の時間変化を追って、ステロイド離脱をサポートするシステムを作ることが必要です。皮ふ科臨床技術への、「理工学的な介入」が必要でしょう。
|
|
4−7 ステロイド離脱の方程式
ステロイドが体内に擦り込まれ、それが体内にいったん蓄積され、最後に体外へ排出される様子は、底に穴のあいたゴム製のバケツに水を汲むのと似ています。蛇口からバケツに水を汲むことを考えます。もしバケツが固い物で出来ていて、穴がなければ簡単です。たとえば、10リットル入りのバケツに毎分1リットルずつ水を汲んだら、バケツは何分でいっぱいになりますか、という算数の問題は小学校3年生が解くでしょう。ところが、バケツの底に穴があいていると、問題は大学生でないと解けません。微分積分の知識が必要になってくるのです。さらに、そのバケツがゴムでできていて、いくらでも膨らむとなると、これはもうたいへんです。しかしこれを「実験」するのは簡単です。ゴムでバケツを作って、側面下部に穴をあけ、それを体重計の上にのせて、蛇口をひねって水を汲み、時間ごとに体重計の目盛りを記録すればよいのです。身体に擦り込まれたステロイドが、蓄積され、排泄される様子も、パターンはこれと同じになります。
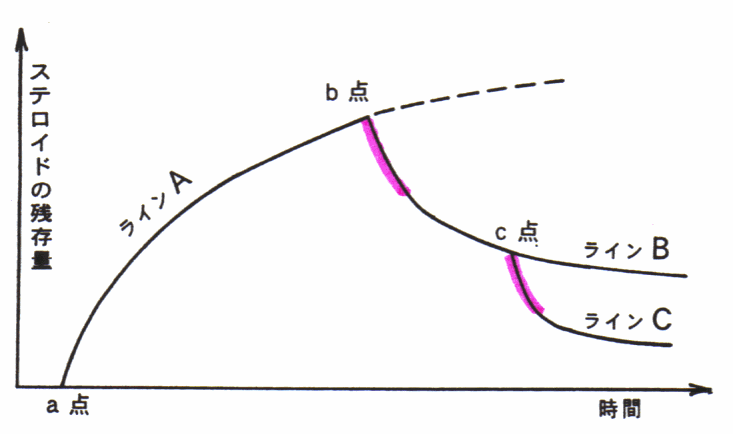 図
ステロイドの蓄積と排出
|
その様子が右のグラフです。縦軸は皮下脂肪に残るステロイドの量、横軸は時間です。
ステロイドを塗り始める(a点)と、その一部は皮下脂肪に蓄積され、「体質なんだからずっと塗り続けなさい」という指示に従って塗り続けるうちに、ステロイドはどんどんたまってラインAのように増加します。
たくさんたまればたまるほど、抜け出す量も増えますから、ラインAのカーブはだんだん緩やかになってきます。
しかし、ステロイドを塗ると皮下脂肪が厚くなり、厚くなった皮下脂肪にさらにステロイドが蓄積される、という悪循環がありますから、ラインAは頭打ちにならずに上昇し続けます。
そこで、ステロイドをやめる(b点)とラインBのようになります。ステロイドは、皮下脂肪から溶け出す一方になりますから、ラインは下降します。初めのうちはラインは急降下しますが、ステロイドの残留量が減ってくると溶け出す量も減ってきて、ラインBはしだいになだらかになります。皮下脂肪から解けだしたステロイドは、血流に入り、全身をめぐってから肝臓などで代謝されて排泄されます。
ステロイドをやめた直後は、ニセものであれ、ともかくも停戦命令であったものがなくなり、「戦闘部隊」だけが取り残されますから、皮ふは外界の刺激に対して激しく反応するようになります。これが、ステロイドをやめたときに起きる最初のリバウンドであり、ステロイド離脱のプロセスで生じるもっとも激しいリバウンドです。
やがて、皮下脂肪からのステロイドの流出量が減ってくると、「戦闘部隊」もしだいに減り始め、皮ふは「準安定状態」になります。
ステロイドをやめると誰でも、遅かれ早かれこの準安定状態に達しますが、ステロイドをやめただけでは、ここから先へは進みません。ラインBのなだらかな状態が長期にわたって続きます。
温泉療法などで3000人以上の人々のステロイド離脱を観察してきた、野村修、周作の両氏は、毎日数時間の温泉浴を続けるという条件のもとで、次のように報告しています。
| 滞留しているステロイドが抜けるのに平均13ヶ月かかっている。 (野村周作 ノムラクリニック 「驚異のアトピー包囲治療」現代書林 1997など) |
しかし何もしなければ、ラインBの状態は寿命より長く続く、つまり、死ぬまでステロイドが抜けないということもあるでしょう。
このような準安定状態では、皮ふは依然として肥厚して固く、深いシワができて、赤みや色素沈着はとれず、ちょっとした刺激にも反応しやすい状態で、妊娠、出産、じんましん、風邪、ストレス、など、さまざまな衝撃によって攪乱されます。何らかのショックで皮下脂肪のステロイドが大量に揺り落とされて血流に入ると(c点)、ラインは急激に下降して、血中に再び「効き目のない古いステロイド」があふれ、それに呼応して戦闘部隊が増強され、再びリバウンドが起こります(ラインC)。このような小さなリバウンドを繰り返しながら、ステロイドはしだいに体外へ排出されてゆきます。
このように、ステロイド離脱は底に穴のあいたバケツ、化学プラントならライン途中のバッファー(緩衝)タンク、医療関係なら点滴ラインの途中のガラスびんのようなものに、液体を注入し、貯え、排出するのと同じ「物理現象」です。ですから、山の高さや下降速度などは人によって違うでしょうが、ラインのパターンは誰でも同じになります。
多くの人々がラインBの「準安定状態」を自分の最終的な到達点だと考え、そこから先は体質だからとあきらめています。しかしそれは間違いです。ステロイドを完全に抜いて、元のゼロレベルの状態にすることで、真の安定が回復するのです。
ステロイドをやめることは、アトピー性皮ふ炎から回復するために避けて通れぬ第1歩です。体内に滞留するステロイドを排出して、ラインをできるだけゼロレベルに近づけるのが、次のステップです。その具体的な方法については第7章に述べます。
第5章 アトピー性皮ふ炎 の 政治と経済
5−1 ステロイドの生産量
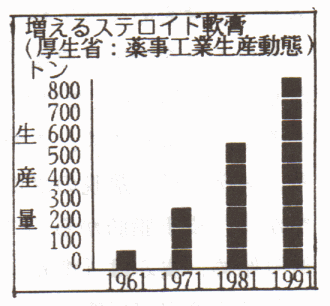 |
右のグラフは、わが国のステロイド外用薬の生産量の推移です。ステロイド軟膏は、1950年代から生産が開始され、最近では年間
800トンを越える生産量になっています。しかも、個々の薬剤の薬効は年々上がってきていますから、薬効で計ればもっと急上昇しています。これらのステロイドはメーカーの倉庫に保管されているわけではありません。すべて国民の、とりわけ若者たちや、子供たちの皮ふに擦り込まれてしまっています。
50年ほど前にはなかった薬剤で、「アトピー性皮ふ炎ではない人に塗るとたいへんなことになる」薬剤で、厚生省が「劇薬指定」せざるを得ないような薬剤が、突然大量に生産されるようになり、そのほとんどの部分が、「アトピー性皮ふ炎の治療」と称して、この30年間、せっせとわが国民の皮ふに擦り込まれてきました。
このような「治療スタイル」は、医薬学業界の主流派の主張に、行政が積極的に協力する形で推進されてきました。厚生省は、平成4年のアトピー性疾患実態調査の後で、「アトピー性皮ふ炎に対する母親たちの不安を和らげる」ことを目的としてハンドブックを出版し、以下のように述べています。
| ステロイド外用薬は、アトピー性皮ふ炎の湿疹病変の治療には不可欠の薬剤である。 ( 「アトピー性皮ふ炎生活指導ハンドブック」 厚生省監修 南江堂 1994) |
しかし、本稿でここまで述べてきたように、厚生省自らが劇薬に指定しているステロイド外用薬を、「原因不明の慢性湿疹」に処方すべきかどうか、大いに議論のあるところであり、むしろ、ステロイドは使うべきではないという声が日増しに強くなっているのが現状です。そんな時に、そのような世論を危惧した「皮ふ科主流派」の意のままに、「ステロイドは不可欠である」と国民に呼びかけることは、行政の態度としてかなり問題があります。これは必ずしも、「母親の不安を和らげる」ことだけが目的ではないのかも知れません。厚生省は薬害エイズ事件において、「血友病治療の主流派」の意のままに、非加熱血液製剤の在庫一掃セールに加担した、と疑われている団体だからです。
いずれにせよ、このような支援に助長されて、医者たちは、それがステロイドであることを告げることなく、副作用について説明することもなく、あるいは、チューブのラベルをはがしたり、ワセリンに混ぜたりなどして、それがステロイドであることを隠して処方する、そんなことがごく日常的に行われてきました。そのことは、各地でのマスコミ取材や、被害者の告発出版、ステロイド被害の裁判などで明らかになっています。
| 30年前、私たち皮ふ科の初年兵は、先輩から「開業したらステロイドを内服させろ」とアドバイスされました。「あの医者はよく治してくれる医者だ」という評判をできるだけ早く広めてもらわねばなりません。その方法として最高なのが、ステロイドの内服だったのです。いまどき、こんな馬鹿げたことをする皮ふ科専門医はいないでしょう。
(西岡 清 東京医科歯科大 皮ふ科 「アトピーは治る」 講談社ブルーバックス 1997) |
これも「告発もの」のひとつです。「いまどきいない」ということは、以前にはそういう「馬鹿げた皮ふ科専門医」がいたわけです。西岡氏の論点は、「ステロイドの内服は馬鹿げているが、外用ならよい」ということでしょうが、本稿では、内服がよいか外用がよいかなどは「論外」として論じません。ともかく、氏が私たちに伝えるのは、今から30年前の医学部では、ステロイド使用が皮ふ科医院の経営と絡めて考えられていたことと、当時はこのような先輩のアドバイスに従った医者もいた、ということです。
要するに、行政も医薬学業界も、必要不可欠、切れ味がするどい、私たちはもうかる、天下り先の意向で、など、その立場立場から、ステロイドを使え使えと30年間言い続けてきたわけです。そして今、何が起きているのでしょうか。
5−2 ステロイド裁判
1996年、筆者は19才の女性を原告として行われた、ステロイド裁判を傍聴しました。原告は1982年、3才の夏に、両足の裏(セキ:足指を除いた、足跡がつく部分。3才児では両足合わせてもハガキの半分くらいの面積か)に湿疹ができ、近所の医者にかかっていましたが、1983年1月19日に、京都の大手の病院を受診しました。
被告である担当医は、M氏という医大を卒業して10年目の皮ふ科医でした。M氏はそれまでの医者と連絡をとることもなく、1週間分としてリンデロンDP(劇薬指定あり
P66)という、強さのランクが上から2番目(Very
Strong)のステロイドを、5g(チューブ1本)処方しました。母親は副作用についてどころか、それが何であるかさえ聞かされなかった、と原告側弁護人は述べ、被告の反論はウヤムヤでした。
1月24日の2回目の診察では、1週間分としてリンデロンDPが2倍の10g処方され、背中にも「鳥肌のような湿疹」があることが確認されて、プロパデルム(劇薬指定なし)という強さが3番目(Strong)のステロイドが、背中用として10g
処方されました。
その後は、カルテも満足に記載されぬまま、この少女にはステロイドが処方され続け、背中の湿疹には、「診察せずにステロイドを処方する」こともあったことが明らかにされました。春休みには、しばらく来ないだろうと「想定」して、1ヶ月分として、リンデロンDP5gx4本が処方されました。塗り方に注意が与えられていなかったので、幼女は厚生省指定の劇薬を、自分でチューブから出して、毎日塗っていました。やがて少女は重いステロイド後遺症になり、15年後にこの裁判になったわけです。
| 日本の医療現場ではインフォームド・コンセント(十分な説明に基づく同意)があまり行われていないので、患者は自分が使っている薬がどういう薬かも分からないという、先進国では考えられない状態で、これが副作用に気づくことが後れる原因となっている。 (水野肇 医事評論家 毎日新聞 1995.5.9.) |
5−3 4割 がアトピー性皮ふ炎の「皮ふ科業界」
わが国では、アンドルー・ワイル氏やハニフィン氏など、来訪する外国人専門家が呆れ返るほどに、「奇妙な皮ふ炎」が蔓延し、ステロイドの大量生産、大量消費に並行するかのように、年々、それは難治化してきています。これに対して皮ふ科主流派を中心とする医者たちは、「アトピー性皮ふ炎は遺伝性疾患だから、完治はあり得ないのだ」と勝手に断定し、それを受けて、「だからステロイドで上手に抑えるしかない」と理屈を立て、「副作用なしに治ることもあるのだから、いい薬じゃないか」と弁解して、しまいには、ネフローゼやぜんそくなどを引き合いに出して、「他の病気にはよく効くのだから、一概に否定するのはいかがなものか」と話を他の病気にすり替えて、あくまでも「原因不明の湿疹に、原因を除去しないままステロイドを塗る」という、自分たちの「流儀」を擁護しています。
しかしこれは、「医薬学」業界に都合のよすぎる理屈と言うべきでしょう。1994年に博多で行われた日本皮膚科学会における市民公開講座で、東京逓信病院皮ふ科(副院長)の戸田浄氏が、口頭でメモを読みあげて開示したデータがあります。
|
東京逓信病院 皮ふ科外来者数(1993年)
(戸田浄氏による)
|
||
| 非アトピー外来 | 10,998 人 X 1.97 回/年 = 21,631 回/年 | 58 % |
| アトピー 外来 | 1,688 人 X 9.34 回/年 = 15,760 回/年 | 42 % |
アトピー性皮ふ炎の人は年に10回近く通院し、皮ふ科外来の42%がアトピー性皮ふ炎だということです。皮ふ科で入院ということはまれですから、外来比率はほぼ全体の比率と一致するでしょう。そしてこの比率は、東京逓信病院だけが特殊なのではなく、また、単に病院経営のことだけでもありません。教授の数、学生の数、ベッド数、研究予算、学会活動など、「皮ふ科医薬学業界」のすべての活動の4割を、アトピー性皮ふ炎という単一の疾患が支えているのです。その背後にはステロイドの売り上げがあります。
逆に言えば、アトピー性皮ふ炎の原因と構造が明らかにされ、問題が真に解決して、アトピー性皮ふ炎という20世紀に発生した奇病が消滅してしまうと、皮ふ科の「業界活動」は現在の6割に縮小されるわけです。その当事者たちに、アトピー性皮ふ炎の真の解決に向かって本質的な努力をしてほしい、と期待することには無理があります。
実際問題として、アトピー性皮ふ炎の原因追求は「アトピー体質論」で行き止まりになっており、そこから先は開かずの扉になっています。立入禁止の標識を乗り越えて、原因を追求しようとする皮ふ科医は、日本にはいません。そして、学会の雑誌を眺めてみれば、原因究明は臨床医の仕事ではない、と言わんばかりの、重箱の隅をつつくような報告が紙面を賑わせているだけで、個々の発見を組み合わせて、「象とは何か」を描き出そうとする試みはありません。それは一種の「事なかれ主義」とも言うべき状況で、そもそも臨床医たちに、病気そのものをなくすように努力してほしいと願うのは、お門違いであることを明示しています。世の中に、自分の仕事がなくなってほしいと願う人は、あまりいないということです。
5−4 皮ふ科主流派が描くアトピー像
現代日本のアトピー性皮ふ炎の「政治状況」を知るには、皮ふ科主流派の考え方を分析する必要があります。その好例として、厚生省の調査委員であり、皮膚科学会の「アトピーの定義と診断基準」の作成者でもあり、マスコミにも登場し、一般向けの著書もある、西岡
清 氏(東京医科歯科大学皮ふ科)の言動を分析するのがよいでしょう。
| 西岡 清 氏は、現代日本の皮ふ科学を代表する碩学、かつ論客である。 (田上八朗 東北大学皮ふ科 メディチーナ 1997.Vol.34-2 P199) |
西岡氏の最新の著書「アトピーは治る」は、講談社ブルーバックスという、国民的な権威のある「科学シリーズ」として出版されたもので、20世紀初頭に出現した「奇妙な皮ふ炎」について、20世紀末にわが国の皮ふ科主流派が到達した地平を示す、貴重な「歴史的資料」であり、皮ふ科主流派の考え方を知るための恰好の材料となっています。
下に紹介するのは、同書の22、23ページの見開きで西岡氏が提示した構図です。あたかも、右大臣ザルツバーガー、左大臣アウグストゥスに守られた「アトピーの祭壇」といった興趣で、祭壇の中央には「アトピー性皮ふ炎の5つの特徴」が祀られています。
|
||||||||||||||
同書において、「アトピーの特徴」をはさんで2つの写真を、このようなシンメトリーの形で提示する積極的な理由は、文脈の上からは見あたりません。しかし本の著者が、ローマ皇帝アウグストゥスはアトピー性皮ふ炎だったと信じ、ザルツバーガーの「体質論」を金科玉条と奉じている人であったなら、編集者の誘導によってはこういう見開きページになりそうです。つまりこれは偶然ではなく、西岡氏の意図を反映したものであり、氏の頭の中で、アトピー性皮ふ炎はこのような構図になっているのでしょう。ザルツバーガー氏は、「アトピー性皮ふ炎」と命名した(P13)皮ふ科の大権威であり、「ローマ皇帝はアトピー性皮ふ炎だった」とは、大先輩の元日本皮膚科学会長の大城戸氏が言うのですから、どちらも祭壇に祀らないわけにはいきません。
それでも、ともかくも氏は、「事実」と確認されているアトピーの特徴を5つ、祭壇の中央に祀っています。これは、「事実」を第一と考える、一応は科学的なやり方です。ところが、これらの5つの「事実」をあげたすぐ次の行で、ただの一言の説明もなく、いきなりそれらをひとからげにして、「アトピーのいちばん大きな特徴はIgE抗体を作りやすい体質ということになります」と、見ず知らずの場所までワープしてしまうのが、常人にはどうにも理解しがたいところです。氏が日本皮膚科学会の「アトピーの定義」を作ったときも、おそらく同じ思考パターンなのでしょう。
どうやら氏の頭の中では、これらの「5つの特徴」と「IgE抗体を作りやすい素因」とをつなぐべき、脳神経のシナプスが欠落してしまっているようで、氏はこのつなぎ目を何度往復しても、自分の論理がワープしていることに気づきません。ですから、これを読んで理解できない人間がいる、ということ自体が理解できないようです。どうせ氏は、「5つの事実」を「IgE抗体を作りやすい素因」という「1つの想像」に昇華させてしまうのですから、氏が祭壇中央に祀るべきは、その「1つの想像」だけで十分で、それでこそ、左右の守護神とのバランスがとれるというものでしょう。
実際この概念は、日本皮膚科学会の総会(1994)で承認されていますから、これが20世紀末におけるわが国の皮ふ科医たちの、アトピーの祭壇の「ご本尊」と言えます。
5−5 皮ふ科と小児科の論争
小児科医もステロイドを使いますし、対象が生後間もない乳児であるだけに責任はいっそう重いのですが、傾向として、小児科医は皮ふ科医より真剣に「原因探し」をしています。アトピー発生の瞬間に立ち会うことが多く、小児科医にとってアトピーとは単に皮ふ炎のことでなく、ぜんそくや鼻炎でもあり、皮ふ科は外科で小児科は内科、という出自の違いもあります。それにそもそも学生の時から、皮ふ科医になりたい学生と小児科医になりたい学生とでは、職業観や人生観が違うのでしょう。
ただし小児科医の「原因探し」は、おおむね除去食の標的探しに終始していますから、問題の解決に役立っているわけではありません。いずれにせよ、アトピー性皮ふ炎の治療法について、皮ふ科医と小児科医は意見が合いません。
日本アレルギー学会という、皮ふ科医や小児科医や内科医などが集まる学会で、1994年に、アトピー性皮ふ炎についての各科の共通理解を図るための議論がありました。
| 西岡 清 東京医科歯科大
皮ふ科 |
皮膚科学会の診断基準では、この「慢性反復性経過」という項目には縛りがついており、乳児では2ヶ月以上となっています。1回だけ湿疹が出現して消えてしまうものもアトピー性皮ふ炎に入れてしまうと、湿疹はすべてアトピー性皮ふ炎になってしまいます。(中略) |
| (それからしばらくしての発言) | |
| 西岡 | 赤ちゃんのアトピー性皮ふ炎などは簡単に治る、1週間で治るというのが私たちの常識なのです。 |
| 浦田章子 如春会 三井病院小児科 |
西岡先生は、乳児のアトピー性皮ふ炎は1週間で治るとおっしゃいましたが、私は、3ヶ月検診でお母さんから、「お薬を塗ればすぐ治るんですけど、また出てきます」という訴えをよく聞きます。 |
| 本村昌子愛和クリニック 内科 |
皮ふ科の先生方はステロイドをよくお使いになります。患者さんは、初めはステロイドを使って早く治ったからよかったといっているのですが、そのうち反発して次の医者に行き、また強いステロイドを使う |
| 西岡 | おっしゃるとおりで、私たちがステロイド依存の治療をしてきたのは否めない事実ですが、ステロイドが悪いのではなく、医者が悪いのです。 |
| (日本アレルギー学会シンポジウム記録集 医科学出版社1994) | |
乳児のアトピー性皮ふ炎など1週間で治る、そんなもん常識じゃないか、と皮ふ科医に挑発されて、小児科医も内科医も我慢がなりません。普段ははおとなしい女性たちも、思わず演壇に詰め寄ってしまいます。皮ふ科医のステロイド頼みには、他科からも批判があるようで、この場は西岡氏も「医者が悪いのです」と引き下がったようです。
ところで、赤ちゃんのアトピー性皮ふ炎など1週間で治るというのは西岡氏の本音で、ステロイドを上手に使うのでしょうが、診断がつくまで2ヶ月待たせて、診断がついたら1週間で治してやる、という氏のやり方は不可解です。どういうことでしょうか。
| かたわらに皮ふ病の写真を置いて、それと見くらべて診断している専門外の医者には適切な診断はできません。そこで皮膚科学会では、簡便な診断基準を作ろうということになりました。つまり、診断基準とは非専門医が誤診を起こさないために作られたもので、十分な知識のある医師には必要ないのです。 (西岡 清 東京医科歯科大 皮ふ科 「アトピーは治る」 講談社 1997) |
なるほど明快です。「縛りがついている」というのも、なんとも奇妙な言い回しだと感じていたのですが、西岡氏らが作った世界に誇るべき診断基準(P65)は、専門外の医者(つまり小児科医とか内科医のことです)を「縛る」ための道具であって、氏自身は、そんなもので自縄自縛にされることはないのでした。
|
小児科医の故松田道雄先生(1−10参照)の名著「育児の百科」(岩波)は、先生の不断の努力によって改訂を重ねてきました。しかしその中に「乳幼児の治りにくい湿疹にはステロイドを塗りなさい」という記述があり、筆者は本書の草稿を先生に送って、その記述は子供たちに甚大な損害をもたらすと指摘し、改訂を求めました。 |
|
|
5−6 専門家がおちいるワナ
| 日本では多くの医者が、「ついでに皮ふ科」を標榜していますが、彼らが皮ふ科についてきちんと研鑽を積んだとは考えにくい状況です。彼らが知っている皮ふ病はせいぜい10種くらいでしょうが、皮ふ病には5万種類ぐらいあります。 (西岡 清 東京医科歯科大 皮ふ科 「アトピーは治る」 講談社 1997) |
西岡氏は他科の医者を切った、返す刀で、未熟な、片手間の皮ふ科医仲間を切り捨てます。西岡氏は熟練のプロとして、皮ふ病を5万種空んじているのかも知れません。しかしそこに、専門家が陥りやすいワナがあります。5万種の皮ふ病でいっぱいの頭には、5万1種目の皮ふ病が入らないということが、実際にしばしば起こるのです。
研鑽を積んだ臨床医と自負し、「私にはわかりません」と言い出しかねる立場にいる人ほど、まったく未知の病気に遭遇したとき、それをなんとか自分の知っている既知の病気にあてはめがちです。そしてどうしても残る、辻褄の合わない部分を、「遺伝性疾患」という「ドラえもんの何でもポケット」に突っ込んで、世間や仲間たちがそれを許せば、それで一件落着となるわけです。
そのことは、水俣病やイタイイタイ病やスモン病の原因探しをする過程で、学会主流の権威者たちの間でも生じました。水俣病を解明した熊本大学医学部の原田正純氏や、イタイイタイ病を解明した富山市の荻野氏や、スモン病を解明した新潟大学の椿忠雄氏などの、あえて言えば「傍流」の人々にはあって、主流派には失われがちなものがあります。それは発想の柔軟性と洞察力です。
眼前の湿疹をアトピー性皮ふ炎と診断することは、「私には分からないということが分かった」と宣言しているだけです。5万種を知って、なお分からない皮ふ病を解明するには、今までの発想を転換し、洞察力を働かさなければなりません。
スモン病について、あらましを紹介しておきましょう。
| 薬害によるスモン 1960年頃から、奇妙な病気が日本で現れはじめた。猛烈な腹痛の後、足先からしびれていく。しびれは鋭い痛みをともなって足にそって上がってくる。しだいに各地で流行するようになり、(中略)伝染病とすればまず原因はウィルスと思われ、1970年ごろからスモンウィルスを発見したという報道が続き、患者やその家族は、(病気をうつされるのではないかと思われて)大変な苦しみを味わった。 多くの研究者が、「やはり常識的にはウィルス感染」と思っていた頃、ある注意深い看護婦の機転が、スモンを解決に導くことになる。東京の三楽病院で働いていた彼女は、入院中のスモン患者につけた導尿管が緑色に染まっていることに気がついた。その物質は東大薬学部に送られ、分析を担当した田村研究室の吉岡正則は、それが、患者が飲んだ整腸剤の主成分である、キノホルムであることをつきとめた。この結果はスモン研究会で報告されたが、キノホルムはありふれた整腸剤だったし、当時はなにしろ、ウィルス説と思いこんでいた人が多かったので、ほとんど関心を持たれなかった。 しかし、1人この結果に注目し、疫学調査を始めたのが、新潟水俣病を経験していた新潟大学医学部の椿忠雄であった。この調査の結果、スモン患者のほぼ全員がキノホルムを服用し、キノホルムを大量に飲んだものほどスモンの症状が重いなど、キノホルムとスモンとの相関を示すデータが集まった。椿は厚生省に報告すると同時に、「1ヶ月遅れると新しい患者が60人増える」と、新聞発表に踏み切った。約1ヶ月後、キノホルムの販売が中止され、患者は激減した。 (黒田洋一郎 東京神経科学総合研究所 「ボケの原因を探る」 岩波新書 1992) |
5−7 バラ色の夢を振りまく皮ふ科主流派
| 21世紀の治療法 遺伝子の解析がすすみ、アトピー性皮ふ炎の皮ふの特徴である易刺激性の遺伝子とその働きが十分あきらかにされたら、遺伝子治療の道もひらけてくるでしょう。IgE抗体産生に関与している遺伝子の解析も進んでいますから、IgE抗体産生も自由に調節できる時代が間もなくやってくるでしょう。 (西岡 清 東京医科歯科大 皮ふ科 「アトピーは治る」 講談社 1997) |
これを額面通りに受け取れば、西岡氏は、アトピー性皮ふ炎は遺伝性疾患であると信じ、遺伝子を操作することが最良の「治療法」であると信じ、それは間もなく実現可能だと、本気で信じていることになります。しかし、そんな「バラ色の未来」は来ません。
なぜ来ないか。それは簡単です。アトピー性皮ふ炎は遺伝性疾患ではないからです。
また、テクニカルな問題としても、「遺伝子をとりかえなければ治らない」と気楽な発言をする人はいましたが(P21)、それは「遺伝子をとりかえれば治る」と言い切るほどの気楽さではありません。受精卵の段階ならいざ知らず、生身の人間の細胞のDNAの中の特定の塩基配列にアプローチすることは、仮にできたとしても、皮ふ科の診察室でちょこちょこと薬を塗るようなことではなく、相応の施設と相応の「研鑽を積んだスタッフ」と、相応の時間と費用が必要な作業です。
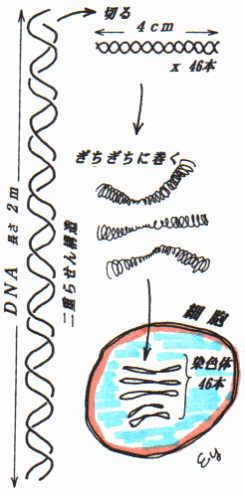 |
遺伝子について簡単に説明しますと、生命体のすべての細胞には、DNA(デオキシリボ核酸)という「二重らせん」構造をした高分子があり、人間の場合は、それは一直線に伸ばすと長さ2メートルにもなり、それは、遺伝情報としては全体で約10万個の部分で構成されており、その10万個のひとつずつを「遺伝子」と呼びます。そのDNAは、直径100ミクロン程度の細胞の中で、4センチくらいずつ46本に分かれて、糸巻き状にギチギチに巻き込まれます。その糸巻き状のものは、染料を加えるとだんだらに染まって顕微鏡で見やすくなることから、染色体と呼ばれています(右図)。
これらの染色体のどこかに、アトピー性皮ふ炎を引き起こす遺伝子があると医者たちは考えているわけで、業界内では、第11番染色体上だとまことしやかに語られているようですが、そこにも数千個の遺伝子があり、どうやってそれを見つけるのか、見つけたらどうするのか、ハサミで切るのか、何百億個もある体細胞をどうするのでしょうか。
皮ふ科主流派に、「遺伝子とりかえ」の具体策があろうとは思えませんが、現実にも、何百万人(体質だけなら4000万人!)ものアトピー性皮ふ炎の人々の「遺伝子」に、なんらかの操作を施すだけの、スタッフも資金もわが国の「皮ふ科医薬学業界」にはなく、たとえ日本中の皮ふ科医を総動員して、10年がかりで1万人ほどの遺伝子にタッチできたとしても、全体がどうなるものでもありません。つまり「アトピーの遺伝子治療」など、理論的にも実践的にも、始めから終いまで正気の沙汰ではないのです。
専門家集団が正気を失うことは、わりとたやすく起こることで、ほんの50年ほど前、帝国軍人はアメリカに勝てると信じ込んでいましたし、ほんの10年ほど前には、銀行も不動産屋も住専も、土地と株は値上がりし続けると夢想していました。いま、住専や銀行が何十億、何百億という金を、当時どのように貸し出していたかを見れば、彼らが正気を失っていたことは明白です。
専門家であるほど、偏向した情報と願望にさらされており、職業的な集団催眠にかかりやすいのです。たかが「奇妙な皮ふ炎」に遭遇したからといって、それがいきなり遺伝性疾患である理由はもともとありませんし、まして先祖伝来の遺伝子を操作しようなどと、考えること自体が臨床医としての職分を越えるものです。そして現実問題として、自分たちの力量を正しく評価する冷静さも欠いているわけで、他のさまざまな兆候から判断しても、皮ふ科主流派は正気を失っているものと思われます。
しかし、西岡氏が、「バラ色の未来など来ない」と正気を保ちつつ、なおこのメッセージを発している可能性も、実はないではありません。その場合は別の解釈になります。さまざまな分野において、指導的立場の人が「バラ色の未来」を強調するとき、それはしばしば現実の矛盾を覆いかくす意図を持っています。「医学界はバラ色の未来に向けて努力しており、その実現は近い」という氏のメッセージは、それが虚偽だと知りながら発したとすれば、「従って国民はそれまでの間、現在のステロイド治療を容認すべきだ」という主張を内包した、現状擁護のプロパガンダ(吹聴)になります。
では、氏はどちらでしょう。実はそれはどちらでもいいのです。「現在の医療技術ではアトピー体質そのものを治すことはできないが・・・・」という
「まえがき」で始まり、「しかし、21世紀には遺伝子治療が可能になる」という「バラ色の夢のあとがき」
で終わるこの書物は、氏の意図はどうあれ、「バラ色の未来」は来ないのですから、現状擁護、皮ふ科主流派擁護のプロパガンダなのです。
5−8 皮ふ科主流派の責任は重い
| もちろん皮ふ科専門医にもピンからキリまであります。つねに新しい皮ふ科学をめざす真摯な医師もいれば、皮ふ科は薬を出すだけでいいから楽な商売だと考える医師もいるでしょう。一般の人がそれを見分けることはむずかしいので、社会的混乱をより深くしています。しかし、親身になって患者さんを心配してくれる、真の皮ふ科専門医も必ずいることを忘れないでください。 (西岡 清 東京医科歯科大 皮ふ科 「アトピーは治る」 講談社 1997) |
西岡氏は、アトピー性皮ふ炎の治療について社会的混乱が起きており、医療側にも問題があると自覚しています。そして氏は、他科の医者を無知と批判し、非専門の医者がついでに皮ふ科の看板をかかげることを批判し、皮ふ科専門医でも心がけの悪い者もいると批判します。要するに氏は、世の中には皮ふ病5万種に精通した、熟練したまじめな皮ふ科専門医と、それ以外の、無知で未熟で不ふまじめな医者がいて、自分は良い医者だが、悪い医者には困ったものだ、という「勧善懲悪論」で世の中を理解しています。
ですから氏が、「私たちがステロイド依存の治療をしてきたのは否めない事実ですが、ステロイドが悪いのではなく医者が悪いのです」と反省するとき、それは、西岡氏以外の医者のことであって、たとえば、本書の冒頭の新聞投書の少年を診察した「大病院の皮ふ科」は、真の皮ふ科専門医ではなかったということであり、5−2のステロイド裁判のケースも、大手の病院だからといって簡単に信用するものではない、ということになります。大病院でさえそうなのですから、2−7の温泉療法の少女の場合も、「近所の皮ふ科医」に行くという行動が、そもそも安易にすぎるということなのでしょう。
しかし、氏のそのような考えは間違いです。現代日本におけるアトピー治療の混迷の本質は、そんな他愛のない「良医VS悪医」の勧善懲悪の物語ではありません。現在のこの混迷は、皮ふ科主流派が事実を認識する能力を欠いて、「アトピーの祭壇」にひざまづくことに発しています。良医だと自負する皮ふ科主流派こそが、その良心の如何ではなく、その「無能」によって、この混迷をもたらしているのです。
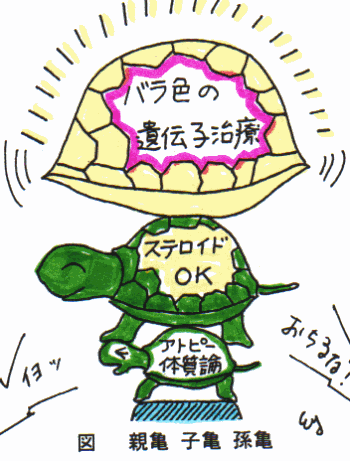 |
1933年という、テレビもコンピューターもない時代、私たちの祖父や曾祖父が満州事変を戦っていた時代に提案された、ひとつの「仮説」に過ぎない「アトピー体質論」を、ローマ皇帝まで動員して膨らませ、その後の調査によって家族歴陽性率が34%しかない(1−3)ことが明らかになった現在でもなお、これは遺伝性疾患なのだと強弁し、ステロイドはやめよ、という大先輩(4−3)を、新しい皮ふ科学を解さぬ古い人間と見下して、「遺伝性疾患だからステロイドは必要不可欠」と自分たちの処方を正当化し、21世紀には遺伝子治療が可能になる、と白日夢にふける、そのような皮ふ科主流派こそが、現在のわが国の「アトピー治療」の大枠を決定してきたのであり、その大枠の中で、外国の専門家たちが怪しみ呆れるような、おそろしいステロイド禍が全国で生み出されてきたのです。西岡氏が批判してやまない、「無知で未熟で不まじめな医者」たちは、皮ふ科主流派の「アトピー体質論の温床」の中でしか、棲息できないのです。
皮ふ科主流派が正気を取り戻し、厚生省の調査結果が示す「真実」を国民に正しく伝え、アトピー性皮ふ炎の遺伝性を否定すれば、親亀はこけて、ステロイド治療を支える主たる根拠は失われます。すると国民はその日から、「アトピー性皮ふ炎ではない人に塗ったら、たいへんなことになる」ような劇薬には距離をおくようになり、ステロイド頼みの乱診乱療は、旬日を待たずして立ち枯れになるでしょう。
「実は、それが困るのだよ・・」ということでしょうか。
アトピー性皮ふ炎に関して、皮膚科学会の中枢が「無能」であり続けていることは、わが国民の不幸と言うしかありませんが、彼らに従っていては、現在すでに2割、やがては3割、4割、5割、の若者たちを襲うであろう悲劇をくいとめることはできません。礼を欠く言い方だ、という反発もあるでしょうが、彼らの主張を諾々として受け入れ、アトピー体質論を認めて、彼らといっしょになってバラ色の未来を夢見ていたのでは、私たちは、私たちの子供たちを守ることはできないのです。
私たちは、科学的で合理的な考えによって、私たちの子供たちを守らなければなりません。
次章で、これまで述べてきたアトピー性皮ふ炎の原理と構造を要約し、合理的なアトピー対策と予防法を述べます。