|
|
|
第3章 アトピー性皮ふ炎の内因
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 元素名 | 1日必要量 | 不足で起きる症状や病気 |
| ナトリウム | 1g-10g | 元気がない 筋肉けいれん 食欲がない もうろうとする |
| カリウム | 2g-4g | 筋肉脱力 しびれ 腸の動きの減少 不整脈 渇き |
| カルシウム | 0.5g-1g | 骨がもろくなる 筋のけいれん しびれ うつ病傾向 興奮 皮ふ、爪の発育不足 |
| マグネシウム | 250mg | 落ち着きがない けいれん ふらつき 不整脈 手足の痛み |
| 鉄 | 10-18mg | 貧血 脱力 無気力 めまい 動悸 |
| 亜鉛 | 10-15mg | 発育遅れる 性的発育が遅れる 味覚異常 皮ふ炎 |
| 銅 | 1-3mg | 貧血 発育不良 ちぢれ毛 血管がもろくなる |
| クロム | 0.3mg | 糖尿病になりやすい 動脈硬化になりやすい |
| ヨウ素 | 0.1-0.14mg | 甲状腺が腫れる だるい むくむ 発育不良 |
上の表は、人体に必要なミネラルの種類と、1日に必要な摂取量、そしてそれが不足したときに生じる障害です。ミネラルの不足という簡単なことでこれほどいろいろな障害が起きてくるのならば、体内にミネラルを適正に補給してやるという、これまた簡単な対策で、たいていの病気は退散してしまいそうです。
厚生省が実施した今年の国民栄養調査で、若者のミネラル不足が指摘されています。調査項目はカルシウムやナトリウム、鉄など主要なものに限られていますが、主要金属が不足しているならば、微量元素も不足しているでしょう。若者たちがなぜミネラル不足になるかというと、彼らの食事が、朝食を食べないとか、昼はハンバーガーなどのファストフード、夜はコンビニで買うレトルト食品、というように、栄養バランスが乱れてきていることが一つの理由です。カルシウムなどのミネラルが不足すると、精神が不安定になり激しい性格になり、イライラしたり、すぐカッとなったりするようになります。海洋民族が、概して大陸民族よりも温和であるのは、海の幸のミネラル摂取量と関係しています。昨今頻発している若者たちの犯罪の凶悪化と低年齢化の根底には、食生活の乱れと、それに伴うミネラル不足があります。若者たちの心理状態の変化の背景には生理状態の変化があり、生理状態の変化の背後には、微量金属元素の不足などという、物質的な、物理的な変化があります。その意味で心もまた物質なのです。
農地から失われたミネラル
では、正しい食生活をしていればミネラル不足にはならないのか、というと、現代の日本では必ずしもそうはいきません。なぜなら、農作物そのものからミネラルが失われているからです。
私たちは子供のころ、ホウレン草には鉄分が含まれていて、鉄は赤い血のヘモグロビンになるから食べなさいと教えられました。アメリカ人は、子供たちにホウレン草を食べさせるために、ポパイにホウレン草の缶詰のイッキ飲みをやらせたものです。
ところがこの表に見るように、今のホウレン草は、40年前の
野菜100g中の鉄分含有量 mg
|
 |
なんと3分の1しか鉄分を含んでいないのです。ニンジンも大根も、鉄分の含有量は半分以下になっています。ですから、昔のように野菜から鉄分を補給しようとすれば、昔の2倍も3倍も食べなければなりませんが、もちろんそんなことは胃の大きさからも、経済的にもできません。
これは鉄に限ったことではありませんし、ホウレン草やニンジンに限ったことではありません。米も麦も大豆も野菜も、日本の農地で作られるあらゆる作物がミネラル不足になっており、何らかの方法で積極的にミネラルを補給することを心がけない限り、日本人はみなミネラルが不足ぎみになってしまっているのです。
なぜそうなったのか。それが本稿の冒頭で「ヤギの生活」にたとえたことです。ホウレン草に鉄分が含まれるのは、それが鉄分を含む農地で作られる限りにおいてであって、鉄分のない農地で作られたホウレン草に、鉄分がないのは当然です。
私たちはこの島国で2000年の間、ずっと農業をしてきましたが、それは常にミネラル分のリサイクルを行いながらやってきたわけです。だから、同じ作物を2000回も収穫し、同じ栄養をとることが出来ました。ところがこの30年ほどの間に、リサイクルの回路はバッサリと切られて、切り口が海側に開放されてしまったのです。農村人口は大量に都会に移動し、都会でも農村でも水洗トイレが普及しました。肥料は石油から作られる化学肥料になり、窒素、燐酸、カリの3大要素はあるものの、あれやこれやの人智の及ばぬミネラルなどは含まれていません。この国の農地のミネラル分は、農作物に姿を変えて都会に運ばれ、そこで消費されて屎尿となり、水洗トイレから海に捨てられて、代わりのミネラルが農地に補充されることはなくなったわけです。さらに、農薬の大量使用によって、土の中のバクテリアが減ってしまっています。土壌のミネラルは、根粒バクテリアの働きによって植物の根から吸収されるのですが、そのバクテリアが農薬によって殺されてしまったのです。
このような農業を全国的に30年も繰り返せば、農作物からミネラルが失われるのも当然で、トマトもキュウリも昔ほどおいしくないのは、こういうわけです。
| 「あのときは本当にショックを受けました。日本は10年、遅れていると実感しました。欧米の有機農法商品が日本に入ってきたら、とても対抗できない」
きっちりした栽培基準、それを第3者が検査する制度、無農薬、無化学肥料だけを「オーガニック(有機)」と表示し市場流通させる明快なシステム。3年前、米国のオーガニック産業を視察したときの気持ちをこう語るのは茨城県共栄ファーム取締役の中村孝治さんだ。 (毎日新聞記事 1997.8.30) |
日本が相変わらず石油化学に頼った、非戦略的な農業を展開している間に、欧米は堆肥や魚粉などをシステム的に用いた有機農法を完成させつつあります。これは結局、生産者の問題ではなく、消費者の問題です。欧米の社会は、自立した市民たちによって構成されていますから、従来型の化学肥料や農薬に頼った農作物は淘汰され、安全で栄養価の高い食物が求められ、それに応える農業が経済的に成立しつつあります。ひるがえって現代の日本では、普通の食事を普通にしていれば健康を維持できる、とは簡単には期待できません。
3−3 亜鉛の欠乏 と 皮ふ炎
さて、前の表でミネラル不足によって起こる障害を見ていきますと、亜鉛が不足する場合には「皮ふ炎」が起きると書いてあります。それは、亜鉛が細胞の新陳代謝に重要な役割を果たしていて、亜鉛が不足すると新しい細胞ができてこないからです。
たとえば、舌の味覚細胞は何かを味わうごとにどんどん消耗されますから、次から次に新しい味覚細胞が作られる必要があり、それが出来ないと味覚異常が起きてきます。ですから、亜鉛が不足すると味覚がおかしくなってきます。成長が遅れるとか、性的な発達が遅れる、傷が治りにくいなどの障害も、細胞の新陳代謝が不活発になるためです。
体内には何種類もの「酵素」と呼ばれるタンパク質があって、物質代謝やエネルギー代謝を効率的にすすめる触媒として機能しています。亜鉛はいろいろな「酵素」の中心的元素として重要な役割を果たしています。細胞の新陳代謝を促進するのは、それらのうちの一つの酵素の働きです。
亜鉛はまた、別の酵素、SOD(活性酸素除去酵素)の重要な構成要素となっていて、亜鉛が不足すると後天的に(先天的にではなく)、
SODが不足するようになります。そして、
SODが不足すると活性酸素が除去できず、皮ふ炎が起きたり、悪化したり、治りにくくなったりするのです。
このように、亜鉛が不足すると、新しい皮ふ細胞が出来にくいことと、皮ふ細胞の周辺で有害な活性酸素を除去しにくいこと、によって皮ふ炎が起きやすくなります。
 |
 |
右の写真の左側は、ドイツ小児科学会誌(Dietrich Matern 博士 V143 P.1255
1995)に報告された、亜鉛欠乏症によって皮ふに炎症やびらんが起きている、生後4ヶ月の乳児です。
母乳だけで育てられていたのですが、何らかの原因で母乳に亜鉛が不足するようになり、乳児が亜鉛欠乏におちいったものです。
右側の写真は、それに気づいた主治医が、その乳児に対して亜鉛の経口補充を行い、その結果、数日間で回復した様子を示しています。
亜鉛不足で皮ふ炎が生じることは、おそらく日本中の小児科医、皮ふ科医が、知識として知っているでしょう。しかし、乳児が皮ふ炎を起こして診察を受けに来たとき、その子の血液中の亜鉛濃度を計ってみるということは、日常の診療ではほとんどありません。どんな大病院にもそういう検査項目がないのです。しかし、亜鉛不足とアトピー性皮ふ炎との間に関連がありそうなことは、すでに学会では報告されています。
我々はアトピー性皮ふ炎児では血清亜鉛濃度が低いものに重症者が多いこと、アトピー性皮ふ炎児の毛髪中亜鉛濃度は対照群に比して有意に低いことを報告してきた。毛髪中の亜鉛濃度は、健常対照児(11例)で158.9±41.1μg/g、アトピー性皮ふ炎児で102.1±25.6μg/gであった。
|
亜鉛を含む食品
亜鉛の摂取量は、アメリカでは、成人1日あたり15mg 、妊婦は20mg
、授乳中は25mg、と勧告されています。妊婦は、赤ちゃんが亜鉛を消費するのでたくさん摂取する必要があります。「つわり」の時に味覚異常が起きやすいのは、亜鉛が不足するためです。授乳中はさらにたくさん必要になります。授乳中のお母さんに亜鉛が不足すると、先のドイツの例のように、乳児が亜鉛欠乏症になることがあります。
ところが日本では、亜鉛の摂取量に公的な基準や勧告はありませんし、実際どれだけ摂取しているかを調べたデータも、20年前の調査があるだけです。それによりますと、その時でさえ摂取量は7mgから8mgということで、十分とは言えない量でした。それからさらに農作物のミネラルが失われてきた現在、亜鉛の摂取量はさらに少なくなっているでしょう。
|
亜鉛の含有量 (単位 mg/100g中)
|
|
| 穀類 | 玄米3.0 白米1.6 小麦1.9 |
| 野菜 | からし菜2.5 ほうれんそう2.0 にんじん葉0.9 |
| いも | じゃがいも0.7 さつまいも0.3 |
| 海藻 | ひじき9.5 わかめ6.4 こんぶ5.4 |
| 種実 | ごま16.0 大豆4.3 |
| 葺類 | しめじ0.7 しいたけ0.4 えのき0.4 |
| 魚 | いわし2.1 さば1.5 えび1.5 いか0.7 |
| 貝 | かき79.0 はまぐり4.4 さざえ2.3 |
| 肉 | 牛肉5.0 豚肉2.7 鶏肉0.7 |
右の表は、食品の亜鉛含有量を示します。あらゆる食品が100gあたりひとケタ
mgの亜鉛しか含んでいない中でカキの亜鉛含有量には驚かされます。カキは特別な貝で、海の中の植物プランクトンを吸収して、亜鉛を濃縮します。縄文時代の貝塚が日本中のあちこちで見つかりますが、そこにはおびただしい量のカキの貝殻が見つかります。ヨーロッパでもカキは海のミルクと呼ばれ、ローマ時代の昔から、フランス、イタリア、スペイン、北欧でさまざまに工夫されてたくさん食べられています。世界中の人々が、カキを貴重なタンパク源、ミネラル源として認識していたことがわかります。
また、1996年に筆者は興味深い見聞をしています。
兵庫県加古川市のある乳児ですが、生まれて4週間ほどしてから、身体のあちこちに湿疹が出てかゆがっていました。(下の写真の左)お母さんはあちこちの病院に連れていきましたが、どこも満員で十分な診察をしてもらえませんでした。
 |
 この赤ちゃんのお母さんの E-mail (現在工事中です) |
そのうち何の拍子か、そのお母さんが産後のダイエットとして、あるメーカーの栄養補給食品を食べ始めたのです。すると母乳を飲んでいた赤ちゃんの肌が少しずつ良くなり、1ヶ月半後には症状はずいぶん改善されて、赤ちゃんは毎日とてもきげんよく元気に過ごせるようになりました。(写真右)
お母さんが食べた食品は、大豆タンパクと、各種ビタミン、ミネラルで構成されていました。その中にはカキから作った貝殻カルシウムも含まれていました。
そのお母さんは大喜びで、かつて診察を受けたことのある小児科医を訪ねて、「こんなによくなりました、母親の私がこれを食べただけなんです、他のみなさんにもきっといいはずです」と懸命に説明したのですが、わが国には、シロウトのそんな経験にいちいち感心する医者はあまりいません。まともに取り合ってくれなかったそうです。
母乳と粉ミルク
では、専門家は乳児の栄養について何を観察しているでしょうか。有田昌彦氏たちは、1993年に全国の1才児と2才児の母親を対象にして、アトピー性疾患と生後3ヶ月までの栄養法との関連を調べるアンケート調査を行い、4610名から回答を得ました。
| アトピー性皮ふ炎の発生率は、完全母乳栄養の乳幼児が17.0%(1958人中333人)、母乳・粉ミルク混合栄養の乳幼児が13.9%(2125人中295人)となり、乳の方が、意味のある差で、アトピー性皮ふ炎になり易い。 (有田昌彦 ありた小児科クリニック ほか 日本アレルギー学会誌V.46-4 P354 1997) |
この結果は、私たちの常識に反します。人間の子を人間の乳で育てるより、牛の乳で育てる方が病気になりにくいとは、いかにも不条理です。しかし、母乳栄養の方がアトピー性皮ふ炎になりやすいというデータはほかにもあって、小児科医たちによる、島根県での調査(1990年)や西日本全域での調査(1992年)でも、そういう結果が出ており、1980年代の後半からは、これはほぼ確定した傾向だと考えられます。
有田氏らはこのデータを、従来から小児科医たちが抱く「アレルギーの先入観」にしたがって、「母乳を通じて、母親から乳児へのアレルゲン感作があるのだ」と解釈し、母親の食事指導の必要性を主張しています。
他方、<ダイオキシン問題を考える会>の高山三平氏は、P4の平成4年度の厚生省の調査報告書を丹念に読みとって、母乳で育った子と粉ミルクで育った子との、アトピー性皮ふ炎発生率の差を「発見」しました。(厚生省調査では、アンケート結果を「母乳か粉ミルクか」といった基本的な統計にさえしていませんから、まわりで苦労して「発見」しなければならないのです)
| 母乳保育と人工乳保育での アトピー発生率 |
|
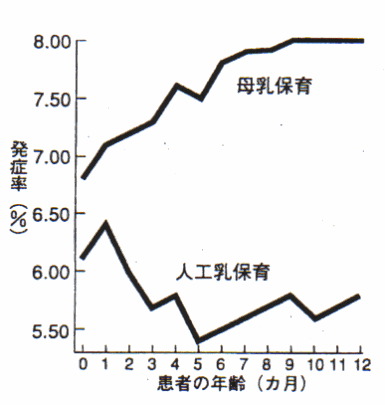 |
|
発見されたデータは、右図のようにきわめて明瞭に、母乳育児の方がアトピー性皮ふ炎になりやすいことを示しています。これも重要な発見です。このデータについて高山氏は、粉ミルクよりも母乳の方が、ダイオキシンを10倍も多く含有しているというデータがあることと、ダイオキシンは免疫系を狂わせる作用があるという事実から、アトピー性皮ふ炎発生率のこのような差は、母乳中のダイオキシンによるものではないか、と推定しています。
しかし、ここにひとつの考慮すべき事実があります。それは、1983年に厚生省が、欧米からの輸入自由化圧力に屈する形で、粉ミルクへの栄養補強剤として亜鉛の添加を認めたことです。もともと母乳には、牛乳よりもたくさん亜鉛が含まれています。それは人間が育つには、牛よりもたくさん亜鉛が必要だからです。栄養学の研究がそのことを明らかにしたので、欧米では粉ミルクに亜鉛を添加して母乳に近づけようとしました。それに習って1983年以降、日本の粉ミルクにも亜鉛が添加されるようになったのです。
| 現在市販されている育児用粉ミルク中には亜鉛塩が強化されているので、亜鉛の必要摂取量が満たされることになる。 (米久保明得 明治乳業中央研究所 「乳汁中の微量元素」 食の科学 V164 1991) |
ところがその一方で、先述したような農業環境の変化によって、日本人の母乳中のミネラルは減少し続けてきました。ですからおそらく、わが国での母乳と粉ミルクとの亜鉛含有量の大小は、遅くとも1980年代の後半には逆転してしまったのではないかと思われます。現代の日本では、母乳で育つ子の方が、粉ミルクで育つ子よりもアトピー性皮ふ炎になりやすい、という不条理を解くカギはここにあると思われます。
小児科医たちは、アトピーはアレルギーだと思いこんでいますから、探すものはいつも、「何か余分に存在するもの(アレルゲン)」です。「ダイオキシン問題を考える会」も、ダイオキシンの問題を入り口にして考えていますから、他の病気は知らず、アトピー性皮ふ炎に限って言えばダイオキシンは無実である、という歴史的な条件を考慮することなく、どうしても思考がダイオキシンに収斂してゆきます。
しかし、これらの人々のように、「母乳の中に何か良からぬものが混入しているのではないか」、という探し方をいくら続けても、「母乳の中に何か足りないものがある」ことを発見することはできないでしょう。加古川のお母さんの母乳から、突然、ダイオキシンが消えてなくなったとは考えにくいことです。このお母さんと赤ちゃんとの共同体験は、ひとつの事実であり、それはアトピーのジグソーパズルのどこかに収まるべき断片です。これらの断片を丹念に拾ってパズルにあてはめていくことで、アトピー性皮ふ炎の全体像はようやく見えてくるのです。
有機農法と食品添加物
アメリカの著名な自然医学者アンドルー・ワイル氏は、前出の書の中で次のように語っています。
| 戦後の日本では農薬と食品添加物の使用量が驚くほど増えているのだ。わたしの日本人の友人に内科を専門とする女医がいるが、彼女によると、無農薬有機食品に替えてアトピー性皮ふ炎が劇的に治った患者が少なくないという。 (アンドルー・ワイル「癒す心、治る力」 前出) |
有機農法とは、堆肥や魚粉などのミネラル分を畑にリサイクルする農法ですから、そこで育った作物にはミネラルが豊富に含まれます。それを摂取することでミネラル不足が解消され、皮ふ炎が改善されるのでしょう。
さらにまた、さまざまな残留農薬や食品添加物が食物に含まれていると、亜鉛が小腸などから吸収されるのが妨げられるという事実もあります。せっかく亜鉛を含む食物をとっても、残留農薬や食品添加物が多いと吸収できないのです。また、有害な化学物質が体内に入ると、それを解毒するために体内での亜鉛消費が増大します。ですから、単に有機農法で亜鉛が含まれることだけでなく、無農薬であることもまた重要なのです。
また、パソコン通信やインターネットを通じて、アトピー性皮ふ炎についての体験談がたくさん語られていますが、その中にも注目すべき発言があります。それは、外国に行くと、短い旅行であってもアトピー性皮ふ炎は著しく改善される、しかし日本に帰ってしばらくすると悪化するという、何人もの体験です。お父さんの転勤で海外に行ったら良くなったという体験は、新聞や雑誌などでもしばしば見かけます。
前章では、アトピー性皮ふ炎の外因は日本に特徴的なものだと考えて、水道水の塩素濃度が世界一であることに着目しました。内因についても、同じように日本に特徴的なことがあるようです。人間は2日も食べずにいると、栄養もカロリーも不足してきますが、体内のミネラルバランスも、行く先々の土地の食物によって、短期間に変わるのでしょう。また、食品添加物についても日本の特殊事情があります。筆者は、スペインのセビリヤで万博が開かれていたとき(1993年)、そこの日本パビリオンで働く日本人の友人から「キューリのKちゃん」という漬け物がほしい、と頼まれて送ったことがあります。しかしそれは、ヨーロッパの税関で通関を拒否されました。「ヨーロッパでは、このような毒物は認められない」ということでした。恐ろしいことです。
ストレスで亜鉛の消費が加速される
亜鉛が不足すると皮ふ炎になるという因果関係は、いったん皮ふ炎になると、逆転してさらに悪循環におちいります。
| 亜鉛不足は、おそらくどの病気にとっても致命的といって過言ではない。どんな身体の損傷でも亜鉛の消費は激しく、特別に亜鉛の補給をしなければ、傷はなかなか治癒しない。 (松浦宏之 女子栄養大学 「微量栄養素のはなし」 技法堂出版 1986) |
アトピー性皮ふ炎の人は皮ふが損傷しており、さらに、皮ふが痒くて掻きますから、いっそう傷がつきます。ですからアトピー性皮ふ炎の人は亜鉛を大量に消費します。
また、受験とか就職、転勤など、さまざまなストレスによって、アトピー性皮ふ炎が悪化することが知られていますが、その背後には、精神的なストレスを受けたときも、それに耐えるために体内での亜鉛の消費量が増えるという、生理学的に確認されている事実があります。つまり、精神的なストレスを受けると体内の亜鉛の消費が加速され、亜鉛不足になって皮ふ炎が悪化する、ということのようです。
アトピー性皮ふ炎で困っている人は、子供たちの場合はいじめなどもあり、身体的にだけでなく、精神的にも強いストレスを受けています。ですから、体内での亜鉛の消費も加速されています。52ページで紹介した、アトピー性皮ふ炎の子供たちは血清や毛髪の亜鉛濃度が低いという事実も、亜鉛不足がアトピー性皮ふ炎の引き金の一つになると同時に、アトピー性皮ふ炎になって、さらに亜鉛不足になってくるものと推測されます。
ミネラル不足がアトピーの内因のひとつ
第1章で述べたように、アトピー性皮ふ炎の人の特徴を見つけて、それをアトピー性皮ふ炎になっていない人と比べてみるだけでは、その特徴がアトピー性皮ふ炎の原因なのか結果なのかは、原理的には分かりません。しかしここまでの考察から、ミネラル(亜鉛)不足は、アトピー性皮ふ炎になった結果として生じる状況でもありますが、アトピー性皮ふ炎を引き起こす引き金の一つでもある、と言えるでしょう。すなわち、
| 外因である塩素などにさらされて、アトピー性皮ふ炎になるかならないかを分ける内因のひとつは、体内のミネラルの不足である |
そして、このように、受胎後および出生後の「環境」によって左右される因子を、アトピー性皮ふ炎の一方の「内因」と考えれば、「同じ遺伝素因を持つ兄弟なのに、どうしてこの子だけがアトピーなのだろう?」という、よくある疑問(にも、部分的に答えることができそうです。
ミネラルのうち、もっとも関係のあるものは亜鉛だと思われます。しかし、生体微量元素の働きは完全に分かっているわけではありませんから、亜鉛に限らず各種ミネラルを適正に摂取することが大切でしょう。また、ミネラルはタンパク質と結合した形でしか小腸から吸収されません。ミネラルはタンパク質の舟に乗って小腸の壁を通るのです。ですからミネラルは、薬剤としてよりも食品として摂取する方が、自然でもあり、のぞましいと言えます。通常の食事で補えない場合は、ミネラルを含む栄養補給食品を積極的に摂取すると良いでしょう。
3−4 リノール酸 と アルファ・リノレン酸
数年前まで、テレビなどではさかんにマーガリンの宣伝をしていました。新開発の植物性のリノール酸という「不飽和脂肪酸」をたっぷり含んでいて、動物性の脂肪で出来ている本物のバターよりも、ずっと健康によいというふれこみでした。ところが最近ではこれらのマーガリンは、商品として販売されてはいますが、テレビや新聞でのコマーシャルは見かけなくなりました。それは、リノール酸のとりすぎが健康に有害であることが科学的に証明されたからです。あれだけの大宣伝のせいで、日本人のほとんどは今でもリノール酸は身体によい、マーガリンやリノール・サラダ油は身体によいと思っていますが、それは間違いで、リノール酸のとりすぎは健康に有害なのです。
リノール酸のとりすぎは、アトピー性皮ふ炎を誘発する内因のひとつとなっている可能性があります。
右の表は、
|
日本人の食事内容の変化
|
||||
| 1946年 | 1960年 | 1998年 | 倍率 | |
| 米 | 115 | 66 | 0.6倍 | |
| 野菜 | 99 | 103 | 1.0倍 | |
| 肉類 | 0.9 kg | 5.0 | 28.0 | 5.6倍 |
| 魚類 | 9.3 | 28.0 | 34.0 | 1.2倍 |
| たまご | 0.4 | 6.0 | 17.0 | 2.8倍 |
| 牛乳 | 1.5 | 22.0 | 92.0 | 4.2倍 |
| 砂糖 | 0.6 | 15.0 | 20.0 | 1.3倍 |
| 油脂類 | 0.1 | 4.0 | 15.0 | 3.8倍 |
戦後の日本人の1人当たりの年間
の食品消費量(単位kg)です。日本人は牛や豚や鶏などの動物性の脂肪(悪い脂肪酸)を大量に食べるようになっています。
右欄の倍率は、1960年と1998年との比率です。戦後すぐの1946年はともかく、もはや戦後ではないと言われた1960年、まだ日本でアトピーが見られなかった頃に比べて、現在の日本人がいかに動物性タンパク質や油脂を大量に摂取しているかがはっきりと分かります。
そしてそれは、老人から若者までを平均してそうなのですから、若者たちだけを見れば脂肪の摂取量はもっと多いでしょう。そして、これから母親になる若い女性の食生活もこのようなものですから、結局これは、母乳を通じた、乳児の食事内容でもあるのです。
脂肪には、飽和脂肪酸と不飽和脂肪酸があります。飽和とは「満席」という意味、不飽和とは「空席あり」という意味です。飽和脂肪酸はその構造として、席が全部満席になっていて、他の物質は入り込めない形をしています。牛肉、豚肉、鶏肉などの動物性脂肪は、飽和脂肪酸を多く含み、常温で固形になります。
不飽和脂肪酸は、構造に空席があって他の物質が入り込むことができる形をしています。植物油や魚油は不飽和脂肪酸を多く含み、常温でも液状を保ちます。不飽和脂肪酸には単価(空席ひとつ)のものと多価(空席たくさん)のものがあり、多価の不飽和脂肪酸はリノール酸とアルファ・リノレン酸に別れています。(下図)
| 注:人間は牛や豚、鶏などの動物より体温が低いため、食事で摂取した動物の脂は、人体内では固まりやすくなります。これが血管などを詰まらせます。魚は冷たい水の中にいますから、常温で固まる油が体内にあっては困ります。ですから、魚油は寒い日には「にこごり」になりますが、常温では固まらず、人体内でも固まりません。ですから動物の脂よりも魚油の方が健康に良いのです。 |
|
脂肪酸の分類
|
||
飽和脂肪酸 |
動物の脂 (牛 豚 鶏) | |
| 不飽和脂肪酸 | 単価 | オレイン酸(オメガ9) オリーブ油、新紅花油、キャノーラ油 |
| 多価 | リノール酸(オメガ6) 紅花油、大豆油、ヒマワリ油、綿実油、コーン油 |
|
| アルファ・リノレン酸(オメガ3) 青背の魚、亜麻仁油、シソ油 |
||
さて、脂肪摂取の全体量はなるべく減らした方が良いのですが、人間には、絶対に必要な脂肪(脂肪酸)があります。それはリノール酸とアルファ・リノレン酸という多価不飽和脂肪酸です。どちらも、体内のさまざまな活動を調整する「調整物質」の原料となる重要な脂肪酸であり、この2つの脂肪酸は、人間はほかの食物から体内で合成することができないので、どちらも食物から直接取り入れなければなりません。その意味でこの2つの脂肪酸を「必須脂肪酸」と呼び、またその化学構造から、アルファ・リノレン酸は別名「オメガ3」といい、リノール酸は別名「オメガ6」といいます。
オメガ3とオメガ6との摂取比率は、オメガ3を1に対してオメガ6を
1.5
くらいが理想的だと考えられています。実際、人々が質素な食事をしていた100年前の開拓時代のアメリカでは、このくらいの比率だったことがわかっています。それが、しだいに肉料理が増え、油で揚げたり炒めたりする料理が増え、ケーキやアイスクリームが増えて、1980年代のアメリカでは、この比率が1対8にまで広がっており、これが現代のアメリカ人の健康に重大な影響を与えています。
わが国では古いデータはありませんが、食生活の変化はアメリカに追随しており、1960年に1対3だったものが、1980年には1対5と広がり、最近はさらに広がっています。これは平均ですから、1対10、あるいは極端な場合は1対100になっている人もいるのが実状で、この変化が、近年のわが国の「生活習慣病」の急増につながっています。
アトピー性皮ふ炎の急増も、このオメガ3とオメガ6のバランスが崩れ、オメガ6の脂肪酸、すなわちリノール酸を取りすぎるようになったことが、内因のひとつとなっていると考えられます。そのメカニズムは、まず、オメガ6の脂肪酸の働きの一つは、体内に吸収されて代謝された結果、「ロイトコリエン4」という物質に変化することで、そのロイトコリエン4とは、動物の体内に炎症を起こさせる機能をもった物質なのです。そして、オメガ3の脂肪酸とオメガ6の脂肪酸は、さまざまな働きにおいてお互いの作用を抑制するように、つまりいつもお互いに牽制してうまくバランスするように働いていて、オメガ3の脂肪酸は、ロイトコリエン4が作り出されるのを抑制する働きがあります。両方が働いて人間の身体はバランスがとれていますから、どちらがいい悪いではありません。バランスが大切です。オメガ6の脂肪酸を取りすぎると、体内バランスが炎症を起こす方に傾くのです。これがアトピー性皮ふ炎の内因として作用しているようです。日本人は全体的にオメガ6の脂肪酸を減らし、オメガ3の脂肪酸の摂取量を増やす必要があります。
オメガ6は、最近の食生活で見慣れた、植物性のサラダオイルや天ぷら油を使った、脂っこいメニューに多く含まれています。ですからまず、脂っこい食事そのものを減らすことが、オメガ6の比率を下げるのに有効です。台所の換気扇に油がベットリとついていたら、あなたは脂肪のとりすぎです。
次に、食用油をリノール酸の多いものから、オリーブ油やキャノーラ油などのオレイン酸の油に替えます。加熱しないで使うサラダドレッシングの油は、アルファ・リノレン酸を豊富に含む「亜麻仁油」や「シソ油(エゴマ油)」にしましょう。
次に魚介類や海藻類を食べるようにします。魚では、青背の魚(青魚)と呼ばれる、イワシ、サンマ、アジ、サケ、マグロなどにオメガ3が多く含まれていて、それはEPA(エイコサペンタエン酸)とかDHA(ドコサヘキサエン酸)という形をしています。
このような食生活で、オメガ3とオメガ6との比率は著しく改善されます。実際、このような考えで食事療法を実践した結果が、学会で報告されています。
| 講演者は永年、アトピー性皮ふ炎に対して伝統的和食に戻す食事療法により成果をあげているが、今回は食事療法前後の脂肪酸の変動を調べた。対象は、平均年令23才のアトピー性皮ふ炎患者32名だった。食事指導は、米、麦、いも、魚介類、大豆類、緑黄色野菜、根菜、海藻類をとり、鶏卵、牛乳、植物油を除去するように指示し4ヶ月間続けた。その結果、臨床面での効果は、著効18例、有効8例、不変6例だった(有効率81%)。血清のリン脂質における多価不飽和脂肪酸のオメガ3とオメガ6の比率は、食事療法開始前の平均
1対5.6 から、食事療法後は 1対2.9 まで改善された。これはわが国の昭和30年代の推測値よりも好ましい値である。 (永田良隆 下関市立中央病院 小児科 小児アレルギー学会誌V.10-3 P.374 1996) |
要するに30年前の日本人の食事に戻ればよいのです。それは世界でも理想的な食事でした。いろいろな宗教に動物を食べることに対する禁忌があるのは、人間は、3度3度ウシやブタやニワトリを殺して食べるようには、もともと出来ていないのでしょう。
オメガ3とオメガ6との違いについての、栄養学的研究の立て役者の1人であった、アメリカのルディン氏は次のように言っています。
| 「オメガ3現象」の著者ルディンは、米国でもオメガ3系列の脂肪酸を使った臨床例がもっとも豊富な医師の1人だ。(略)オメガ3というただ1つの栄養素で、これだけ全身的な改善が見られるのは驚異だが、ルディンは別に驚くにあたらないと語っている。 「私は、調子の悪い自動車が持ち込まれたときに、優秀なメカニックならだれでもすることをしただけです。患者のオイルを替えたのです」 (豊かさの栄養学② 丸元淑生・康生 新潮文庫 1991) |
また、シアトル郊外で23年間、「タホマ・クリニック」を開いて予防栄養学を実践している医者のジョナサン・ライト氏は、次のように語っています。
| 「私のクリニックではアトピー患者に対して、必ず脂肪酸分析をおこなっています。アトピー患者に典型的な脂肪酸のパターンはリノール酸の数値は高いのに、それから作られるはずのオメガ6系列の脂肪酸の数値がことごとく低いというものです。同時にオメガ3系列のEPAやDHAの数値も低すぎます。こうしたケースではガンマ・リノレン酸を与えるのが最も効果的です。実際、このような患者には、月見草油とEPA、ビタミンB6と亜鉛を与えると、症状は劇的に改善します。亜鉛の欠乏もアトピー患者には大変多いのです。また、オメガ3系列の脂肪酸が不足するケースも多いのですが、その場合は、アルファ・リノレン酸の豊富な亜麻仁油を与えています。 (豊かさの栄養学② 丸元淑生・康生 新潮文庫) |
ライト氏が「アトピー患者」というとき、それはアトピー性皮ふ炎には限定されていません。実際、ミネラル補給や脂肪酸バランスの改善は、ぜんそく、鼻炎、花粉症などのいわゆるアレルギー疾患にもきわめて有効であることが、数多く実証されています。
脂肪酸のアンバランスもアトピーの内因のひとつ
アトピー性皮ふ炎になると、必須脂肪酸のうちオメガ3のアルファ・リノレン酸だけが特別に消費されるという事実はありません。また、必須脂肪酸は体内では合成できません。ですから、もしアトピー性皮ふ炎の人の必須脂肪酸のバランスが、一般の人よりオメガ3が少ないとすれば(そういう大規模な統計調査はまだありませんが)、それは食事によって生じた偏りであり、したがってそれはアトピー性皮ふ炎の結果ではなく、アトピー性皮ふ炎の原因側のファクターだと推論されます。つまり、
| 外因である塩素などにさらされて、アトピー性皮ふ炎になるかならないかを分ける内因のひとつは、体内の不飽和脂肪酸がアンバランスなことである |
マーガリンは食べない
マーガリンやショートニング(味のないマーガリンのこと。パンやケーキのつなぎに使われている)は避けるべきです。それらは単にリノール酸というだけでなく、植物油などに水素添加して人工的に作られた不飽和脂肪酸で、「トランス型脂肪酸」という形になっていて、もとの性質が失われて有害性が高いからです。植物油は常温では固まりにくいと前述しましたが、マーガリンは液体では困ります。それで水素を加えて、常温で固形にするのです。
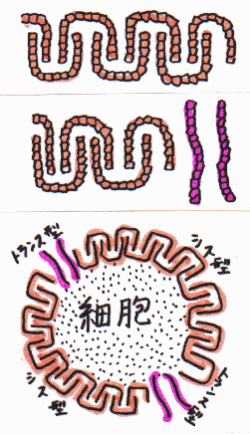 |
体の細胞のひとつひとつは、細胞膜でおおわれています。皮ふの細胞も同じです。脂肪酸はその細胞膜を構成する物質です。細胞膜が、マーガリンやショートニングなどに由来するトランス型の脂肪酸で形成されると、その細胞膜は弱くて働きが悪いものになり、皮ふ細胞の場合は有害物質の侵入を許しやすくなって、皮ふトラブルの元となります。
右図の上段は「シス型」の自然の植物油の構造で、中段は水素添加されてトランス型になった脂肪酸です。
下段はそれらの脂肪酸によって作られた細胞壁のモデル図で、一部トランス型の脂肪酸のところで細胞壁が切れてしまっている様子を表しています。
欧米諸国ではすでに、トランス型の脂肪酸を含む食用油の一部は販売禁止になっており、トランス型の脂肪酸を含まないマーガリンが、「トランス・ファット・フリー」と表示されて販売されるようになっています。その基準を適用すれば、わが国のマーガリンのほとんどが販売禁止になります。これを放置していることもまた、日本のアトピー問題を深刻にしている、わが国特有の条件のひとつと言えるでしょう。
3−5 母体のステロイド濃度 と 新生児の過敏性
この節では、少し不確定なことを述べます。はっきりは分かっていなくても、危険は避けたほうがよいということです。それは、母親がステロイド剤を使っていた場合に、胎児にどういう影響があるかという推測です。医薬学業界では、「何の影響もありません」と屈託のない話をしていますが、本書をここまで読んでこられたみなさんは、そのような「太鼓判」をあまり信用する気にはならないでしょう。
同愛記念病院の向山徳子氏たちは、
| 同病院で出生した368人の新生児について、出生時に臍帯血(ヘソの緒の血。胎児の血です)のIgE値を検査しておき、その後3年間にわたって、その子たちの気管支喘息とアトピー性皮ふ炎との発生状況を追跡して、出生時の臍帯血のIgE値が
0.5以上あるかどうか(成人のIgE値は正常で100くらい)をひとつの目安にして、その統計を分析した。 (向山徳子ほか 小児アレルギー学会誌 V.7-3 P.134 1993) |
そこに、「出生時の臍帯血のIgE値と、家族歴と、その後のアトピー性疾患の発症率」(論文の第9図)という統計があり、家族に「アレルギー疾患」の病歴がある場合は、子の臍帯血のIgE値が0.5以上になる確率が高く、出生時に臍帯血のIgE値が
0.5以上である場合は、その子がアトピー性疾患を発病する確率が高いことを示しています。
家族歴の有無と臍帯血IgE値との関係 |
出生時のIgE値とアトピー発症との関係 |
まず、「家族歴の有無」と、臍帯血のIgE値との関係を見ますと、左の表のようになっています。家族にアトピー歴がある子は368人中143人いて、そのうち37人(26%)の子が、出生時のIgE値が
0.5以上になっています。家族歴が無い子は、225人で、そのうちIgE値が 0.5以上の子は
12人(6%)しかいません。
次に、出生時のIgE値と、アトピー性疾患の発生率との関係を見ますと、右の表のようになっています。出生時のIgE値が
0.5以上だった子は 49人おり、そのうちの34人(なんと70%)が、3年以内にアトピー性疾患を発症しています。一方、IgE値が 0.5以下だった子は
319人で、そのうちアトピー性疾患を発症した子は71人(22%)です。
アトピー性疾患を発症した子のうち、出生時のIgE値が0.5以上だった子の34人に対し、0.5以下だった子が71人で2倍以上もいますから、0.5以下だからといって安心はできません。しかし0.5以上だと、何らかのアトピー性疾患になる確率は「7割」もあるわけですから、十分注意が必要だということです。
論文には、家族歴として「2親等までを調査した」とあるだけで、その内訳は不明です。
筆者は、「母親」の「アレルギー歴」が、子の出生時のIgE値と強い相関をもっているだろうと考えていますが、この論文からはそこまでは分かりません。
ところが最近、大阪医大の佐々木聖氏は、以下のように報告しています。
| 新生児のIgE値を測定し、その後のアレルギー疾患発症状況を6年間追跡した。新生児IgE値が0.5IU/ml以上で、母親にアレルギー歴がある場合は87.5%の子に、父親にアレルギー歴が有る場合は37.5%の子に発症を見た。また、新生児IgE値が3.0IU/ml以上の場合、全例(100%)が6才までにアレルギー疾患の発症を見た。 (佐々木 聖 大阪医科大学小児科 日本アレルギー学会誌 V.45 No.89 P829 1996) |
母親と父親のアレルギー歴に着目し、父親のアレルギー歴との相関は、母親のアレルギー歴との相関の半分以下であると指摘しています。実は、2親等以内の家族歴といったおおざっぱなやりかたでなく、きちんと続柄ごとにアレルギー歴を見ていくと、母親との相関の方が父親との相関よりも強いことを示するデータは、たくさんあります。(それらを詳細に分析すれば、おそらく父親との相関は、「子は親に似る」以上のものでないことが分かるでしょう)
父親からの影響と母親からの影響が対等でないという事実は、アトピー性疾患は遺伝子によって伝達されてはいないという、本書の推論を支持する事実だと考えられます。そして、母親の影響の方が強いということは、アトピー性疾患の発症には、妊娠、出産、授乳という、母子が密着している期間の「環境因子」が作用していることを示していると考えられます。
出生時にIgE値が高い子がいるのは、受胎後の母胎内での環境による「後天的」なものでしょう。IgEというものの設計図は、もちろん遺伝子に書かれています。そうでなければIgEという精巧な機械を作れるものではありません。しかし、それをどれだけ作るかという「細かい話」は現場合わせでやることになっています。遺伝情報とはそういうものであって、設計図はすべてそろっていますが、それをどのように発現させるかについては、「環境に合わせて適当に振る舞え」とファジイなことしか書いていない部分も多々あるのです。だからこそ、たとえば寄生虫が体内に入ればIgEは増加することが「できる」のであり、環境に合わせて変化することが「できる」のであって、日本皮膚科学会が言うような、「IgE抗体を産生しやすい素因」などがあるわけではないのです。
胎児にとっての環境とは、すべて母親ですから、胎児は母親の血液中のIgE値を参考にして、外界に出たときに必要だと思われる自分のIgEレベルを決めるでしょう。ですから、母親のIgE値が高ければ、胎児のそれが高くなるのは自然です。それは遺伝子に書かれていることではなく、後天的な学習効果です。
では、母親のIgE値はなぜ高くなるのでしょうか。向山氏も佐々木氏も、「母親のアレルギー歴」を追跡しています。それは「遺伝論」あるいは「体質論」から来る着想ですが、アトピー性皮ふ炎は遺伝ではなく後天的なものだとすれば、母親のアレルギー歴は重要ではありません。それに代わって何か後天的で人為的な影響が対置されるべきです。筆者は、それはおそらく母親の「ステロイド使用歴」だろうと考えます。
現代の日本では、アレルギーの母親のほとんどがステロイドを使っていますから、アレルギー歴とステロイド使用歴はほぼ一致しています。ですから、アレルギー歴をステロイド歴と読み替えることによって、統計数値の変動はないでしょう。そして、ステロイドを使い続けると、次章の4−3、4−4に述べるようなプロセスで、体内のIgE値は高くなってゆくと思われます。
ですから、次のような、左から右への連鎖的なプロセスが起きていると推測されます。
|
→ |
|
→ |
|
→ |
|
→ |
|
出発点を「母親のアレルギー歴」から「母親のステロイド歴」に書き換えたことに対して、そんな連鎖のメカニズムは発見されていない、と医者たちは反論するでしょう。しかし出発点にステロイドを置くことで、「アトピー性皮ふ炎はなぜ増えるのか」という、体質論では解けない謎を、部分的にせよ説明することができます。また、出生時のIgE高値という現象を、先天的なものとあきらめる必要がなくなり、それを防ぐ可能性も見えてきます。佐々木氏が発見したように、出生直後のIgE値が3.0以上だと、6才までになんと
100%!の子が何らかの「アレルギー疾患」になるのですから、その子たちがアレルギー疾患にならないように後から気をつけるよりも、その子たちがIgE高値で生まれてこないように、合理的と思われる予防策をとる方が賢明でしょう。
本書の第1章で紹介した大阪教育大学のデータでは、女子学生の
23%がアトピー性皮ふ炎になったことがあり、15%が今なお症状に悩んでいます。すなわち現代の日本では、これから子を生む女性たちの中に、幼時にステロイドの影響を受けたであろう女性が
23%、現在でもステロイドを使っているであろう女性が 15%もいて、その人たちが子を生み、生まれた子たちがアトピーになりやすいという、「アトピーの第2世代」に入りつつあるのです。
日本中の人々がアトピー性皮ふ炎になれば、理論的にいって、家族歴陽性率は100%になります。これは単純な算術の問題です。ですから、1987年に50%、1992年に34%、と低下してきたアトピー性皮ふ炎の家族歴陽性率(第1章参照)は、現在のアトピー性皮ふ炎の増加傾向が続くと、いずれ必ず上昇に転じます。そしてそうなれば、「アトピー体質論」は再び力を得てしまい、アトピー問題を解決するチャンスは遠のくでしょう。ステロイドはその傾向を加速しています。60年にわたって医者の幻想にすぎなかった「アトピー体質」というものが、皮肉なことに、ステロイドによって「医原的」に作られつつあるのです。
「ホルモン」は未解明のものであり、その影響も未知のものです。たとえ医者は気づかなくても、母胎のステロイドホルモンの濃度が異常に高いことは、子の過敏性を高め、子のアトピー性疾患発症の内因となっている可能性があります。
| 外因である塩素などにさらされて、アトピー性皮ふ炎になるかならないかを分ける内因のひとつは、母胎のステロイド濃度が高いことである |
これから妊娠、出産される人は、ステロイドを使っているならそれはやめて、さらに体内からステロイドを抜くように、第7章で述べるような工夫をすべきでしょう。