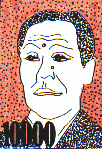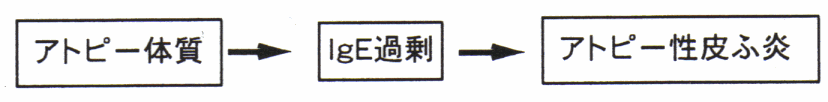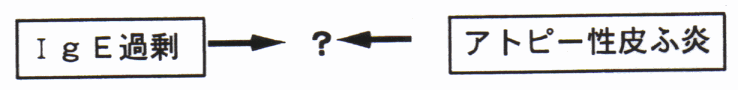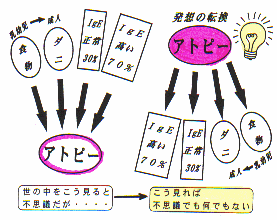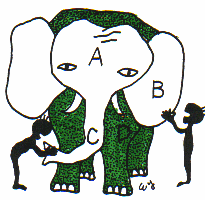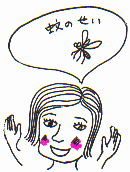|
医者はなんでも断定的に言う方が患者に信頼される、という教育が行き届いているのでしょうか。まるで見てきたような屈託のなさです。
あるいはまた、民間で温泉療法をすすめている小川秀夫氏は、アトピー性皮ふ炎の人を次から次に調べて自律神経失調症の人が多いことを観察し、「したがって、自律神経の失調がアトピー性皮ふ炎の原因である」と主張しています。(アトピー性皮ふ炎の治し方がわかる本:小川秀夫著 かんき出版
1992)
あるいはまた、アトピー性皮ふ炎になっている人の精神面や家族関係などに着目して、アトピー性皮ふ炎の人は、わがままな人が多いとか、家族関係に問題がある、などという事実を発見して、それがアトピー性皮ふ炎の一因だと主張する医者も散見します。
これらの人々はすべて、すでにアトピー性皮ふ炎になっている人たちを観察して、まだアトピー性皮ふ炎になっていない人との違いを見い出せば、それがすなわちアトピー性皮ふ炎の因果関係を示すことになる、と考えているわけです。
アトピー体質論の呪縛
しかし、アトピー性皮ふ炎に限らず、そのような作業をどれだけ積み重ねてみても、ものごとの因果関係を知ることはできません。そのような空間での比較作業で、時間方向の動きである「因果」の順逆を見い出すことは、原理的に不可能なのです。先にも見たように、アトピー性皮ふ炎の人は、皮ふの角質がザラザラしているとか、IgE値が高い、とかの特徴を見つけても、それだけではそれらの特徴がアトピー性皮ふ炎の原因をなすものか、アトピー性皮ふ炎になった結果であるかは分かりません。
しかし臨床医たちは、角質がザラザラしているのは先天的だ、IgE値が高いのは先天的だ、SOD誘導能が低いのは先天的だ、バリアー機能が低いのは先天的だ、と勝手にそれらを先天的なものだと決め込んでおいて、先天的なものが結果であるはずはなかろう、したがってそれはアトピー性皮ふ炎の原因だ、と断定するわけです。ずいぶん勝手な話ですが、ここにあるのも「体質論の呪縛」です。
しかし一方、この種の情報を統合すれば、因果関係が推定できることもあります。多くの医者たちが、すでにアトピー性皮ふ炎になっている人々を思い思いに観察して、いろいろな特徴を探り当てたわけです。それらの特徴はたがいに排他的なものではありませんから、同じ人に同時に生じてもいいはずで、これらの医者たちがそれぞれ自慢の測定器なり測定手法を持ち寄って、ある1人のアトピー性皮ふ炎の人を観察すれば、皮ふがザラザラしている、IgE値が高い、
SOD誘導能が低い、バリアー機能が低い、自律神経失調、家族関係がおかしい、などということがいっぺんに発見されるでしょう。そしてもしそうなれば、俺が、俺が、と言い張ることはないわけです。これらの特徴が個別にアトピー性皮ふ炎の原因であるとは考えにくく、これらはすべてアトピー性皮ふ炎になった結果(症状)だ、と認識する方が合理的です。
たとえば、「この人はもともと皮ふの角質がザラザラしているタチだったので、アトピー性皮ふ炎になったのだ」と考えるより、「この人はアトピー性皮ふ炎になって、角質がザラザラしてきた」と考える方が私たちの日常感覚に合っていますし、同じく、「この人は不幸なことに細胞間脂質が少なく生まれついてしまったために、アトピー性皮ふ炎になったのだ」と、わざわざ倒錯的に考えるより、「アトピー性皮ふ炎になると皮ふに穴があいて、皮ふ細胞の間をつないでいた水分や油分が蒸発してしまうから、細胞間脂質などが減ってしまうのだ」と考える方が合理的です。痒くて夜も眠れなければ、自律神経にも変調をきたすでしょうし、親にも甘えたくなるでしょうし、わがままも言いたくなるでしょう。これは、ハタ目には明らかな因果関係です。要するにここでも、臨床医たちは「体質論の呪縛」にがんじがらめになっているのです。
ただし後述しますが、これらの特徴の中で、SOD誘導能の低下だけが「原因側」である可能性があります。それは先天的なものではありませんが、体内のミネラル不足によって起きる現象だからです。
群盲、象をなでる
かつて日本アレルギー学会は、自分たちのアレルギー疾患についての研究状況は、「群盲象をなでる」ような状況だと、いささか自嘲気味に言ったことがあります。しかし、このことわざは、盲目であることを揶揄したり、卑下したりするものではありません。得られた情報は統合されなければならない、という教訓です。自分が見つけたことだけから、象はウチワのようなものだとか、象は丸太のようなものだなどと言い張って、他の人が見つけたものと比較照合しようとしない愚かさを戒めているのです。ですから、医学界が「群盲象をなでる」状態にあることはその通りでしょうが、その状態は本人たちの「素因」に由来するものではなく、本人たちの自覚によっていくらでも改めることができるのです。嘆いている場合ではありません。
1−9 「アトピーの遺伝子」を追うムダ
しかし、アトピー体質論に凝り固まってしまうと、さらに常識はずれのビックリするようなことを、平気で言うようになります。
|